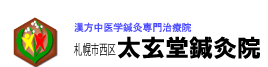ごあいさつ ~太玄堂鍼灸院 院長福田毅より~
太玄堂鍼灸院の名前の由来
 みなさまはじめまして。太玄堂鍼灸院院長の福田毅です。まずは当院の名称である太玄(タイゲン)の由来から述べさせていただきます。
みなさまはじめまして。太玄堂鍼灸院院長の福田毅です。まずは当院の名称である太玄(タイゲン)の由来から述べさせていただきます。
「太」は、ふといまたは目上の人などの呼び名につける尊称をあらわし、「玄」はくろい色、天の色、奥深くてよくわからない微妙な道理という意味があり、『説文解字』などには「幽遠也」また「黒にして赤色あるものを玄と為す」とあります。『老子』の第一章に「・・・この両者は同じきより出て而も名を異にす。同じく之を玄と謂い、玄の又玄、衆妙の門。」という言葉もあります。
つまり、東洋医学という奥深く、深遠で微妙な道理を体現(そう、「タイゲン」です)できる鍼灸院になりたい、また鍼灸治療、東洋医学を通して、みなさまとともに成長できることを願い、太玄堂鍼灸院と名付けました。この名に恥じないよう日々研鑽していきたいと思っています。
太玄堂鍼灸院のロゴマーク
ともに信頼し、幸せの訪れを願って

太玄堂鍼灸院のロゴマーク(シンボルマーク)ですが、人と人が手を取り合い、ともに成長し、幸せが訪れますようにという願いを込めています。
治療というものは、ともすると、治療家から患者へと一方通行のやりとりになりがちです。ところが、実際は、治療家と受診者との信頼関係、「気」と「気」の交流がとても大切です。そこで、「幸福が訪れる」「幸せの再来」という花言葉をもつ「すずらん」を背景に配置し、鍼灸師とみなさまがともに手をとりあっている様をモチーフとしました。
ふたりの人が手を取り合っていますが、どちらが鍼灸師でどちらがみなさまということはありません。黄色と赤は、月と太陽を表しており、東洋医学(中医学)において、陰陽(月と太陽)の融合はとても重要なキーワードとなっています。鍼灸治療を通して、互いが月と太陽のような関係となり、疲れた体と心を癒し、ともに幸せになっていきましょう。
すずらんの花ですが、実は札幌市の「市の花」でもあります。すてきな花言葉を持つすずらんの花を市の花とする札幌市で、鍼灸院を開くことができたことを喜ばしく思っています。
すずらんの花言葉
 幸福が訪れる、幸せの再来、幸福が戻ってくる、幸福、純潔、純愛、清らかな愛、繊細、フランスでは「聖母の涙」とも呼ばれているそうです。
幸福が訪れる、幸せの再来、幸福が戻ってくる、幸福、純潔、純愛、清らかな愛、繊細、フランスでは「聖母の涙」とも呼ばれているそうです。
「すずらん」の花は、幸せを奏でるチャペルの鐘のように、小さな鈴がいくつも連なっています。「すずらん」を贈ると相手に幸福が訪れると言われており、意中の相手にすずらんを贈れば、幸せなゴールが待っているかもしれません。
太玄堂鍼灸院院長福田毅の略歴
1968年北海道生まれ
茨城大学理学部生物学科卒
サラリーマン生活を経て、鍼灸師をめざすことを決意。北海道鍼灸専門学校卒
東京や大阪の治療院勤務を経て、奈良の藤本蓮風先生のもと藤本漢祥院にて3年間内弟子となり、東洋医学(北辰会方式)の研鑽をつむ。
2005年(平成17年)5月 札幌市に西区に太玄堂鍼灸院開院。
東洋医学・東洋思想に興味を持つ
私が鍼灸師になったいきさつをお話したいと思います。もともと子どもの頃からずっと東洋思想に興味がありました。いまの西洋の近代合理主義が生んだ急ぎ過ぎの時代において、何か重要なものが抜け落ちているのではないか、そしてそれは東洋の文化の中にあるのではないかという思いにかられていました。
答えはありました。人が本当の生をいきるにはどうすればよいのかということが、東洋思想・東洋医学のなかに説かれていました。それは単なる概念ではなく実効性があり、治療効果のあるものなのです。 例えば、最近では当たり前の話題になりましたが、人と自然・社会環境についての関係が、東洋医学では述べられています。
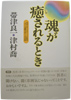 『魂が癒されるとき―気功・ホリスティック医学・ガン治療をめぐる対話』(創元社、1996年)という津村喬/帯津良一両先生の本の中でも、「昭和30年代、高度成長まえの生活水準に戻るだけでも、石油の消費量を200分の1に落とすことができ、その頃の生活に戻るのが大事だ」という趣旨のことが書かれていますが、『黄帝内経』という東洋医学のバイブル的な本の中でも、「ゆったりとしたこころもちで生活できなかったり、養生を間違えているために昔の人のように長生きできないのだ」(上古天真論篇)と書かれおり、同じ内経のなかに、季節ごとの詳しい生活の仕方(四気調神大論篇)や、食べ物と人との関係(宣明五気篇など)についても書かれています。
『魂が癒されるとき―気功・ホリスティック医学・ガン治療をめぐる対話』(創元社、1996年)という津村喬/帯津良一両先生の本の中でも、「昭和30年代、高度成長まえの生活水準に戻るだけでも、石油の消費量を200分の1に落とすことができ、その頃の生活に戻るのが大事だ」という趣旨のことが書かれていますが、『黄帝内経』という東洋医学のバイブル的な本の中でも、「ゆったりとしたこころもちで生活できなかったり、養生を間違えているために昔の人のように長生きできないのだ」(上古天真論篇)と書かれおり、同じ内経のなかに、季節ごとの詳しい生活の仕方(四気調神大論篇)や、食べ物と人との関係(宣明五気篇など)についても書かれています。
この黄帝内経の中では、漢方薬よりも鍼が中心に書かれています。漢方薬のバイブルとされる『傷寒論』のなかでも鍼についての記載があります(太陽病24条)。また山田慶兒先生の『中国医学はいかにつくられたか』(岩波新書、1999年)のなかでも、「中国医学を作り出せることになったものは鍼灸療法であることを、内径と難経は象徴的に物語っている」(P24)と書かれています。
サラリーマンになってはみたが、やはり鍼灸師になりたい!
 このように極論すれば東洋医学の根幹である鍼灸医学に常に目を向けていました。しかし諸事情から一度はサラリーマンとなりましたが、東洋医学への夢は捨てがたく、サラリーマンを辞し鍼灸学校に入学しました。
このように極論すれば東洋医学の根幹である鍼灸医学に常に目を向けていました。しかし諸事情から一度はサラリーマンとなりましたが、東洋医学への夢は捨てがたく、サラリーマンを辞し鍼灸学校に入学しました。
北海道鍼灸専門学校を卒業後、勉強のため東京や大阪の治療院に勤務しました。そのとき北辰会という東洋医学の学術団体に出会い、会員となりました。2年間の一般会員を経て、より深く北辰会方式の理論と技術を学ぶため、北辰会の代表である藤本蓮風先生のもと内弟子として「藤本漢祥院」で3年間修行し、東京時代を含めると5年間学ばせていただきました。そして平成17年5月より札幌市西区で開院し、現在に至っています。
北海道発、東洋医学発信基地をめざす
当院は小さな鍼灸院ですが、志は大きく、北海道の東洋医学・鍼灸医学を発信する地になりたいと思っています。 また、ひろい意味でいい鍼灸師(人としても、治療家としても)になりたいと思っています。
その他福田の好きな言葉・趣味など
日頃感じていること
いのちの不思議。
1本の鍼、ひとつまみのモグサでも変化する身体の不思議を日々感じています。
日頃思っていること
患者も自分も納得、そんな鍼灸をすること。
好きな言葉
「至誠天に通ず」
「まごころをもって接すれば、それは天まで通じて、必ず人を動かすものだ。」という孟子の言葉です。
好きな食べ物
好き嫌いなく何でも食べます。あえて好きな食べ物をあげるとすれば、日本そば、和食、中華などが好きですね。
特に日本そばは、東京、大阪、奈良滞在中も、おいしそうなそば屋さんを見つけては食べに行っていました。因みに北海道は、日本そばの生産が第1位なんですね。私のそば好きもそのあたりのことが関係しているのかもしれません。
趣味・好きなもの
読書。面白そうな本は、ジャンル問わず読みます。特にチャンバラ小説(時代小説)や落語が好きです。詩や俳句も一時期よく読みました。好きな作家ですが、時代小説では、池波正太郎さんや藤沢周平さんです。池波さんの作品の中で、『剣客商売』なんかいいですね。みなさんは、時代小説や歴史小説は好きですか?
☆池波正太郎関連書籍
『剣客商売』 (新潮文庫)
☆藤沢周平関連書籍
『蝉しぐれ』 (文春文庫)
 好きなものといえば、落語もそうです。落語に関していえば、中学生のときに講談社文庫で興津要さんの古典落語のシリーズを読んだのが最初です。その後、立川談志さんの『現代落語論2』などを読んで落語ファンになりました。(まだ中毒症状は出てませんが・・・・・・)談志さんのほかに好きな噺家は、桂枝雀さんです。
好きなものといえば、落語もそうです。落語に関していえば、中学生のときに講談社文庫で興津要さんの古典落語のシリーズを読んだのが最初です。その後、立川談志さんの『現代落語論2』などを読んで落語ファンになりました。(まだ中毒症状は出てませんが・・・・・・)談志さんのほかに好きな噺家は、桂枝雀さんです。
何かで東京に行ったときには末広亭や浅草演芸ホールなど行ったりもしますが、本で楽しむことのほうが多いです。以前、談志師匠が札幌に来られたのですが、また札幌で談志さんの落語が聴きたいです。談志師匠には怒られるかもしれませんが、落語の話のなかでは人情話が好きです。
※大変残念なことですが、2011年11月21日に談志師匠がお亡くなりになりました。生で談志さんの落語が聴けなくなるのは残念ですが、今後も談志さんの本やDVDなどで拝見・拝聴し古典落語に親しみ続けたいと思います。ご冥福をお祈りいたします。
☆立川談志師匠関連書籍
『現代落語論―笑わないで下さい』 (三一新書 507)
☆桂枝雀師匠関連書籍
『上方落語 桂枝雀爆笑コレクション〈1〉スビバセンね』 (ちくま文庫)
☆興津要関連書籍
『古典落語』 (講談社学術文庫)
ほかにも詩・俳句も好きです。残念ながら、作るだけの才能はないため、もっぱら読んで楽しんでいます。詩とくらべると俳句を鑑賞することはあまりないのですが、なかでも尾崎放哉が好きです。尾崎放哉は種田山頭火とならび称されますが、どちらかというと山頭火のほうが有名ですね。放哉には何故か惹かれます。尾崎放哉の俳句を味わうサイトも紹介していますので、興味があるかたは一度ご覧ください。
詩でいえば宮澤賢治、中原中也、黒田三郎などを読みました。宮澤賢治は詩だけでなく童話も好きです。私が特に好きなのは『グスコーブドリの伝記 (宮沢賢治絵童話集)』という童話でした。黒田三郎は詩集『詩集 小さなユリと』が心に残っています。
話は変わりますが、海援隊の「思えば遠くへ来たもんだ」(※アルバム『エッセンシャル・ベスト 1200 海援隊』に収録)の歌詞は、中原中也の「頑是ない歌」(※「在りし日の歌」31番目の歌。参考書籍『中原中也詩集 (新潮文庫)』)の詩のフレーズからとってます。
映画はそれほど頻繁には見ないのですが、「ライムライト」 って映画が好きです、時代を超えたすばらしさを感じます。かのチャールズ・チャップリンが監督・主演をし、1953年に公開された映画ですが、いまだに泣けます。私が生まれるはるか前に公開された映画ですが、いい作品はいつまでも見続けたいですね。
鍼灸師ということもあって、東洋の伝統文化・東洋の伝統医学は最も関心が高い分野ですが、欧米を中心に広まっているアロマテラピー、ホメオパシーなどの癒しの技術や、アメリカインディアン、オーストラリア大陸のアボリジニなど、先住民族の文化についても、とても関心があります。