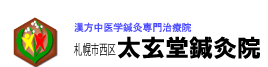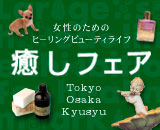太玄堂鍼灸院の鍼灸治療について
太玄堂鍼灸院の鍼灸治療について
太玄堂鍼灸院のサイトをご覧いただきありがとうございます。太玄堂鍼灸院院長の福田毅と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 患者の皆様に
患者の皆様に
当院では患者さん一人一人により適するために、東洋医学を基礎としながらも西洋医学などの他の様々な知見も活用した当院独自の総合的な施術を行います。
また、患者の皆様の健康と幸福の為に少しでもお役に立てるように、微力ではございますが日々精進いたします。
※詳しくは「太玄堂鍼灸院の鍼灸治療」、「施術を受ける際のお願い」や「太玄堂鍼灸院へのよくあるご質問」をご覧下さい。
 我が街札幌の冬の見どころ・イベント
我が街札幌の冬の見どころ・イベント
 さっぽろホワイトイルミネーション
さっぽろホワイトイルミネーション
さっぽろホワイトイルミネーションは、日本で最初のイルミネーションとして1981年にはじまった冬の札幌を彩るイベントです。
2025年で第45回目を迎えます。開催期間は、2025年11月21日(金)~2026年3月14日(土)の予定です。
会場によって開催期間が異なります。詳しくは「さっぽろホワイトイルミネーション公式サイト」をご覧ください。
 |
 |
| 2024年第44回 | 2022年第42回 |
 |
 |
| 2017年第37回 | 2015年第35回 |
 |
 |
| 2013年第33回 | 2010年第30回 |
 さっぽろ雪まつり
さっぽろ雪まつり
1950年にはじまり2025年で第76回目を迎えます。開催期間は2026年2月4日(水)~2月11日(水・祝)の予定です。
さっぽろ雪まつりは、地元の中・高校生が6つの雪像を大通公園に設置したことをきっかけに始まりました。1974年以降札幌とつながりの深い外国地域の雪像が制作され、国際色あふれるイベントとして発展しました。雪氷像は美しさとともに、その時代の世相も表現しています。
会場は、大通会場、すすきの会場、つどーむ会場と3つあり、雪像や氷像、巨大すべり台など、会場ごとに趣が異なります。それぞれの見どころポイントをチェックして冬の札幌をたっぷり満喫してください!
詳しくは「さっぽろ雪まつり公式サイト」をご覧ください。
 |
 |
| 2025年第75回 | 2024年第74回 |
 |
 |
| 2023年第73回 | 2019年第70回 |
 |
 |
| 2018年第69回 | 2017年第68回 |
 北海道の鍼灸専門学校
北海道の鍼灸専門学校
北海道には現在鍼灸を学ぶための専門学校が3つあります。
鍼灸に興味がある方は、「鍼灸師になりたい」なども参考にされ、鍼灸専門学校を一度見学されてはいかがでしょうか。
詳しくは「都道府県別鍼灸専門学校・大学・盲学校一覧」の中から興味ある学校を選び、それぞれのウェブサイトをご覧ください。
●北海道青葉鍼灸柔整専門学校
北海道札幌市中央区南3条東4丁目1-24
TEL:011-231-8989
●北海道鍼灸専門学校
※福田の母校です。
北海道札幌市西区山の手2条6丁目
TEL:011-642-5051
●北海道メディカル・スポーツ専門学校
北海道恵庭市恵み野北2-12-4
TEL:0120-498-369
 『癒しフェア ―Body Mind Spirit―』
『癒しフェア ―Body Mind Spirit―』
心とカラダそして地球にやさしい癒し関連の商品・サービスを一度に体感できる総合見本市です。
毎年、東京、大阪、福岡で開催され、癒し関連に関心の高い企業・サロンオーナー・バイヤー・一般女性の方々が多数来場されます。
また、各方面の著名なゲスト方々が多数来られるのも大きな特徴です。
詳しくは『癒しフェア』のサイトをご覧ください。
 開院日・定期休診日について
開院日・定期休診日について
本院は原則として定休日なしで開院いたしております。
※都合により臨時にお休みをいただく場合がございます。
※臨時休診日につきましては、当サイトにてお知らせ致します。ただし、緊急の場合は当サイト上に反映できない場合もございますので、念のためお電話でご確認くださいますようよろしくお願い致します。
 アクセス
アクセス
〒063-0824
札幌市西区発寒4条4丁目4番21号
コーポ鈴木101号室
TEL:011-664-5354
JR函館本線発寒中央駅南出口徒歩5分
地下鉄東西線発寒南駅1番出口徒歩5分
 鍼灸治療症例集
鍼灸治療症例集
 鍼灸治療体験談
鍼灸治療体験談
 神経系の症状
神経系の症状
「三叉神経痛から右顔面、全身へ広がった神経痛の治療体験談(T.Tさん)」
【関連する症状:歯痛】
妊娠中に神経痛に悩まされ、どの病院でも「そのうち治ります」と言われたものの、終わりの見えない激痛に堪え兼ね、鍼灸治療を受けられたかたの体験談です。
 消化器系の症状
消化器系の症状
「虫歯治療後の歯の傷みの治療体験談(K.Hさん)」(※追加更新:2017年6月6日)
歯痛の原因は様々です。虫歯が原因であれば歯科治療が中心となりますが、鍼灸治療によっても痛みを取ることが可能であるという症例です。
現代はストレス社会です。ストレスによる胃腸の痛みを抱える方も多くいらっしゃいます。鍼灸治療はストレスによる胃腸の痛みなどにも効果的な治療法の一つです。
 呼吸器の症状
呼吸器の症状
 皮膚科の症状
皮膚科の症状
「顔の痒み(かゆみ)・紅斑(こうはん)の体験談(A.Aさん)」
 産婦人科(女性の方特有)の症状
産婦人科(女性の方特有)の症状
K.Sさんは、病院で不妊治療をしながら、当院の鍼灸治療を受け、無事妊娠されました。
当院の鍼灸治療は、身体のバランスを整えながら妊娠しやすい身体づくりのサポートを致します。
「風邪(かぜ)、食欲不振と生理痛の治療体験談(H.Kさん)」
太玄堂鍼灸院の逆子の鍼治療は、ケースによって通常の鍼と刺さない鍼を併用いたします。
詳細は「逆子の鍼灸治療について」、「使用する鍼について」をご参照ください。
また、安産のお灸も指導いたします。お灸をするツボについても、個別指導いたします。
☆「『妊婦は太っちゃいけないの?』(2007年1月)(2007年1月)」より
本書『妊婦は太っちゃいけないの?』は、著者ご自身の妊娠出産の経験も踏まえて書かれた本です。
東洋医学に関する話がたくさん出てきます。妊娠・出産を控えた方はぜひお読みください。
 小児科(子ども)の症状
小児科(子ども)の症状
おたふく風邪は治るまでに7日~10日かかるとされます(『病気がみえる 〈vol.6〉 免疫・膠原病・感染症』より)。
鍼灸治療で軽めに早めに良くなった事例です。
「憤怒痙攣(泣き入りひきつけ)と夜泣き・疳の虫の治療体験談(R.Fさん)」
小児はり(小児鍼)治療を受け、あまりに気持ちよくて、治療後寝てしまうお子さんもいらっしゃいます。「子どもに鍼灸治療って、怖がるんじゃないかしら?」とご心配のお母様もご安心ください。
 その他(ウイルス性・不正愁訴など)
その他(ウイルス性・不正愁訴など)
 「院長の独り言」について
「院長の独り言」について
鍼灸・東洋医学にまつわる話題を中心に、民間薬草や健康食材にまつわる話、鍼灸・東洋医学・健康に関する一般書などをご紹介しています。ぜひご覧ください。
 「院長の独り言」年度別直近3か月
「院長の独り言」年度別直近3か月
※最新記事は、
「院長の独り言」年度別をご覧ください。
- 2026年年始のご挨拶(2026年1月)

- 『赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア』(白川美也子著、国永史子訳、春秋社)(2025年12月)
- 『からだは嘘をつかない』(アレクサンダー・ローエン著、国永史子訳、春秋社)(2025年11月)
 「院長の独り言」ジャンル別
「院長の独り言」ジャンル別
○東洋医学・鍼灸などの参考文献○
『弁釈鍼道秘訣集』(緑書房)
『昭和鍼灸の歳月』(績文堂)
『鍼灸真髄』(医道の日本社)
『脈診を語る』(東洋はり医学会)
『中国医学史講義』(燎原書店)
『中国医学の歴史』(東洋学術出版)
『中医趣談』(広西師範大学出版部)
『画像ではわからないしつこい腰の痛みを治す本』(講談社)
本書は釧路労災病院脳神経外科部長である井須豊彦医師が一般の患者さん向けに書かれた腰痛の本です。非常にわかりやすく書かれており、私たち鍼灸師も患者さんへの説明の参考になります。









 「院長の独り言」ダイジェスト“冬”
「院長の独り言」ダイジェスト“冬”
☆豆まき(2017年2月)
2月の節分に豆をまく理由は、無病息災を祈るほか諸説あり、陰陽五行という東洋思想が関与する面白い説もあるのですが…。
詳しくは「豆まき」をご覧ください。
☆七味唐辛子(2014年12月)
七味唐辛子は、江戸時代に徳右衛門が両国薬研堀にて漢方薬を参考にして作ったのが始まりで、それが全国に広まったと言われています。
七味唐辛子使われる主な生薬の働きを東洋医学的に見てみますと…。
詳しくは「七味唐辛子」をご覧ください。
☆冬の食べ物(2014年2月)
冬の食べ物というと、個人的に思い浮かぶのは、長いも、レンコン、大根、みかんなどですが、それらの東洋医学的な働きを見てみますと…。
詳しくは「冬の食べ物」をご覧ください。
☆冬は寒邪と腎の臓にご注意を(2014年1月)
東洋医学では気候が人体に与える影響は大きいもので病気の原因にもなると考えられています。
冬はこの中の寒が大きなウエイトを占めるのですが、寒(寒邪)の特徴とはいったい…。
詳しくは「年始のご挨拶 ~冬は寒邪と腎の臓にご注意を~」をご覧ください。
☆甘酒(2011年11月)
甘酒には酒粕に砂糖を加えて作ったものと麹から作ったものの2種類があります。
現代では甘酒は冬の飲み物ですが、江戸時代には夏バテ防止のため飲まれていました。どのような成分と働きがあるかと言いますと…。
詳しくは「甘酒」をご覧ください。
☆寒さと脈の関係(2006年10月)
私は日々の治療で患者さんの脈を診ているのですが、寒くなってくると脈に特徴があらわれてきます。
明らかなカゼ症状が出ていない人でも、よく診てみるとカゼに反応するツボに反応が出ているのですが…。
詳しくは「寒さと脈の関係」をご覧ください。
☆「カゼ」について(2005年12月)
冬になるとどうしても「カゼ」を引きやすくなりますね。東洋医学では「カゼ」は、大きくは傷寒と温病と考えられています。
私たちが通常さむけを伴なっておこる「カゼ」は傷寒です。「カゼ」も体質などにより漢方薬が異なるのですがいったい…。
詳しくは「「カゼ」について」をご覧ください。
 「院長の独り言」特別編
「院長の独り言」特別編
 「かんたん中医学講座」について
「かんたん中医学講座」について
全10回を通して、中医学理論の基礎を学んでいただける講座です。
2023年12月に最終回『第10回「鍼灸について」【鍼灸書籍と心持の大事】』を公開いたしました。