「院長の独り言」ジャンル別
「院長の独り言」ジャンル別~日本の伝統行事編~
旧正月と小正月(2024年2月)
明治時代に、暦が新暦(太陽暦)に変わる以前は旧暦(太陰太陽暦)でした。
旧正月とは旧暦の正月のことで、二十四節気の雨水(新暦2月19日頃)の直前の朔日(新月)が旧暦の元日となります。
新暦では年によって1月22日〜2月19日までの間を移動することになります。
小正月は新年最初の満月つまり旧暦1月15日のことでした。
中国から伝わってきた旧暦(太陰太陽暦)は、新月から新月までを基準にして1ヶ月としますが、それ以前の日本では満月から満月までを1ヶ月と捉えていました。
中国と同じように、旧暦1日1日(新月)を正月とするようになってからも、満月の1月15日を「小正月」と区別して呼び、原始的な日本人の感覚による新年のスタート「小正月」は受け継がれていきました。
現在では新暦(太陽暦)の1月15日が小正月とされています。
豆まき(2017年2月)
2月の節分には豆をまきますが、では何故豆をまくのでしょうか?
その理由として様々な説があります。
もともと豆まきは中国から伝わった風習ですが、豆は「魔滅(まめ)」に通じ、無病息災を祈る意味があるというもの、鬼の目(魔目=まめ)に投げつけて鬼を退治したからというものなどです。
豆まきは一般的に、一家の主人あるいは年男が炒った豆をまくものとされています。(現在はお子さんや家族みんなでまく方が多いのではないでしょうか。)
このときにまく豆は炒った豆でなくてはならないとされています。
なぜなら、生の豆を使うと拾い忘れた豆から芽が出てしまうと縁起が悪いからだそうです。
一般的にはこのように説明されていますが、次のような面白い説もあります。
古代においては一年の始まりは春からでした。(年賀状にも迎春と書きますね)
春は五行思想では「木」となりますが、五行の関係で「金克木」となることから穏やかに春(木)を迎えるには「金」を避けねばなりません。
「金」は形としては円い性質をもっています、豆も円いので、豆を「金」と見立てて、その「金」を弱めるために(火克金)火で豆を炒るのです。
そして炒った豆(弱った金)をまく、つまり投げつて傷めつけることで「金」を更に弱め、更に食べて無くすことにより、一年の始まり(春=「木」)を穏やかに迎えるというものです。
一家の主人あるいは年男が炒った豆をまくというのも、古代においては儀式は本来男性、特に家長の役割でした、また年男は新しい一年を暗喩しているのかもしれません。
様々な説があるので、どれが正解かは分かりませんが豆まきという行事の成立にも陰陽五行という東洋思想が関与しているとしたら面白いですね。
端午の節句と菖蒲(2012年5月)
5月5日は端午の節句ですね。
端午の節句はもともとは菖蒲の強い香気で厄を祓ったり、よもぎを軒につるしたり、菖蒲湯に入ったりすることで無病息災を願いました。それで菖蒲の節句とも言われます。
それが菖蒲が尚武と同じ読みであることから、男の子の節句とされ武者人形や鎧や刀を飾ったり、鯉のぼり(男子の出世の意味がある)を飾るようになったようです。
ちなみに東洋医学では菖蒲は開竅薬に分類されます。開竅薬とは芳香があって気付け薬として使われるものです。
菖蒲の性味は、辛・苦、温。
菖蒲の帰経は、心・脾・胃。
菖蒲の働きとしては、除痰開竅(意識障害などに)、醒神健脳(不眠、健忘、痴呆などに)、化湿開胃(食欲不振などに)、聡耳(難聴、耳鳴りなどに)といったものがあります。
お盆のお墓参り(2007年8月)
もう8月ですね。当院は8月の14日、15日をお盆休みとさせて頂きますが、実家に帰ってお墓参りでもしようかと思っています。
ちなみにお盆は仏教の盂蘭盆(うらぼん)が由来とされていますが日本独自の風習と合わさって出来たもののようです。
仏教の盂蘭盆は釈迦の弟子の目連尊者が亡くなった母親の姿を探すと、餓鬼道に堕ちているのを見つけて、水や食べ物を差し出しましたが、母親の口には入りませんでした。 釈尊に相談すると、すべての比丘に食べ物を施せば、母親にもその施しの一端が口に入るとのことで、その通りに実行して母親の口にも入ったというものです。
それと日本に昔からあった先祖供養の風習が合わさって今のお盆の風習になったようです。
また地方によっては施餓鬼(せがき)と呼ばれ、餓鬼道に陥った亡者を救ったりなどの風習も行われるようです。
いずれにしてもその中心にあるのは、日々の生活に感謝し、親切に施しをする心を大切に育てようというものかも知れません。
他人を思いやる心の無い世界は考えただけでもゾッとしますものね。
もうすぐ節分ですね(2006年1月)
もうすぐ節分ですね。皆さんは節分って何だか知っていますか?
節分は元々季節を分けることを意味し立春、立夏、立秋、立冬の前の日のことです。節分が特に立春の前の日を意味するようになったのは、昔は冬から春の境である立春から新しい年が始まると考えられていたからです。ちなみに四柱推命などの占いでも立春からその年の始まりとし立春まえは前の年として計算します。
節分といえば豆まきですが、元々は「追儺(ついな)」と呼び中国から伝わった風習のようで、疾病などをもたらす悪い鬼を追い払う儀式で文武天皇のとき慶雲3年(706年)に宮中で初めて行われたそうです。
皆さんご存知のように節分のこの日は炒った豆を年神に供えた後その豆を年男が「鬼は外、福は内」と声を出しながら豆を蒔きます。このとき蒔かれた豆を、自分の年の数または年の数より一つ多く食べて一年の無病息災を願います。
このように鬼たちにとっては節分はツライ1日でありますが、名字に「鬼」の字が付く家では「鬼は内、福は内」というそうです。
まあ~確かに、自分たちが家から追い出されたら大変ですよね。
また奈良県吉野、蔵王堂の節分会では「福は内、鬼も内」といい全国から追い出された鬼を救い仏門に帰依させる行事があります。 これぞ仏の慈悲。
京都の八坂神社では新しい年の福を持ってくる福鬼を迎えるという一般の豆まきとは逆の行事があります。この福鬼に頭をなでてもらうと一年の厄が免れるそうです。
鬼たちが聞いたら泣いて喜びそうですね。
ちなみに、節分の行事として、その年の恵方(えほう、良い方角)に向かって巻き寿司を食べる「恵方巻き」や「鰯(いわし)の頭も信心から」ということわざで有名な鰯の頭を柊(ひいらぎ)の小枝に刺して戸口に挿すという風習もあります。
節分といってもいろいろあって面白いですね。
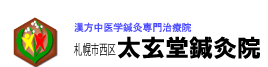
 院長の独り言メニューへ戻る
院長の独り言メニューへ戻る 院長の独り言ニューへ戻る
院長の独り言ニューへ戻る