「院長の独り言」年度別
2012年1月~6月の「院長の独り言」
- 『サトル・オステオパシー』(ザカリー・J. コモー著、たにぐち書店)(2012年6月)
- 端午の節句と菖蒲(2012年5月)
- 鍼灸楽(2012年4月)
- 『飲むお茶、食べるお茶 ミャンマー紅茶物語』(磯淵猛著、PARCO出版)(2012年3月)
- 漢字で見た陰陽五行(2012年2月)
- 2012年新年のご挨拶 ~江戸しぐさ~(2012年年始)
『サトル・オステオパシー』(2012年6月)
『サトル・オステオパシー―伝説のオステオパス ロバート・フルフォード博士に学ぶ叡智』(ザカリー・J. コモー著、たにぐち書店)は伝説のオステオパシー治療家であるロバート・フルフォード(1905~1997)について書かれたものです。
オステオパシーとは簡単に言うと米国で生まれた整体です。
フルフォードはオステオパシーの治療家の中ではどちらかというと異端のようで、オステオパシー自体が自然治癒力という生気論を背景にしているのですが、より進み彼の言葉ではエーテル体(東洋医学の気と似た概念)に対する治療を模索していく過程が興味深かったです。
ウォルター・ラッセル、ランドルフ・ストーン、ブレンダ・ジョンストン、ロバート・ベッカー、ヴァレリー・ハント、キャンディス・パートなど当時の思想家や学者、治療家など様々なところからアイデアを得ながら自分なりの真理を追究していたのだと思います。
本書を読んで思ったのですが、フルフォードは単なる臨床家ではなく、人間とは、生命とは何であるかを探求する哲学者だったのではないでしょうか?そんな気がしました。
東洋医学・鍼灸も気一元、生気論の立場ですが、改めていろんな角度からの情報を参考にしながら東洋医学・鍼灸とは何か、人間とは何か、生命とは何か、という問いかけを日々続けていくことが大事なのだと思いました。
端午の節句と菖蒲(2012年5月)
5月5日は端午の節句ですね。
端午の節句はもともとは菖蒲の強い香気で厄を祓ったり、よもぎを軒につるしたり、菖蒲湯に入ったりすることで無病息災を願いました。それで菖蒲の節句とも言われます。
それが菖蒲が尚武と同じ読みであることから、男の子の節句とされ武者人形や鎧や刀を飾ったり、鯉のぼり(男子の出世の意味がある)を飾るようになったようです。
ちなみに東洋医学では菖蒲は開竅薬に分類されます。開竅薬とは芳香があって気付け薬として使われるものです。
菖蒲の性味は、辛・苦、温。
菖蒲の帰経は、心・脾・胃。
菖蒲の働きとしては、除痰開竅(意識障害などに)、醒神健脳(不眠、健忘、痴呆などに)、化湿開胃(食欲不振などに)、聡耳(難聴、耳鳴りなどに)といったものがあります。
鍼灸楽(2012年4月)
数学、科学、経済学、言語学など堅苦しい「学」のつく学問が多いなか「音を楽しむ」と書いて音楽とは素晴らしいと、かねがね思っていましたが、この解釈は明治以降のあとから生まれた俗説だそうです。
楽にはたのしむという意味もありますが、口から出る音が「音」で楽器から出る音が「楽」で、学問としての音楽は正式には音楽学というのだそうです。
ちょっとがっかりしましたが、しかし楽しんで学ぶということの大切さは変わらないと思います。
古代ギリシアでは哲学を含む総合的な学問として「フィロソフィー(知を愛す)」という言葉がありますが、知るということ自体楽しいことであり、だからこのような言葉が生まれたのだと思います。
これはすべての学問について当てはまるでしょうが、私の専門は鍼灸なので、「フィロ鍼灸」、「鍼灸楽」と改めて宣言したいと思います。
『飲むお茶、食べるお茶 ミャンマー紅茶物語』(2012年3月)
『飲むお茶、食べるお茶―ミャンマー紅茶物語』(磯淵猛著、PARCO出版)の著者磯淵猛さんは紅茶研究家で本もいくつも出されています。
ミャンマーにはもともと茶の原木があり、ロエサイペタミャータオンド寺にお茶の伝説があるそうです。
ロエサイペタミャータオンド寺は今から2000年も前に建てられ、孔雀を神の象徴として崇めてきました。
800年ほど前バガン王国のアラウンシドゥ王がこの寺を訪れた時、近くの川で捕えたミャンという鳥が7羽王に奉納されました。このうち2羽ののどが膨らんでいたので中のものを取り出すと何かの木の実でした。王は村の長老にこれを神の実として授けました。長老はその実を受け取る際、王にひざまずき、うやうやしく右手を差し出しました。普通、物をいただくときは両手を出すのがどの国でも一般的ですがこの村では片手で受け取るのがもっとも敬意を表す方法でした。そして長老がこの実を植えたところ、茶の木になった、というものです。
片手のことをミャンマー語で「レテ」、葉のことを「ペ」、それで茶葉のことを「レテペ」というのだそうです。
レテペは緑茶にもされ、その場合はラペチョウと呼ばれ、紅茶にした場合は、ラペイエ。さらに飲むばかりではなく、漬物のように茶葉を1年、2年と漬け込み、サラダ油をかけて、ゴマ、揚げたニンニク、ピーナッツやそら豆とあえて、お茶うけにして食べもします。これはラペットといいます。こんなふうに茶葉を丸ごと飲んで、食する民族、しかもそれが国民食となっている国は無いそうです。タイや雲南省では、一部の民族が食するだけだそうです。
ミャンマーの紅茶専門店で飲むラペイエはよーく煮出した紅茶液に、たっぷりのコンデンスミルクを沈め、スプーンで何十回もかき混ぜて、甘いミルクティーにしてから飲むのだそうです。
お茶の文化が国によって異なりるのはとても面白いことですが、お茶を食べる文化があるというのは驚きでした。
お茶は中国が発祥の地で、お茶の呼び方も中国福建省アモイ系の発音タイ(TAY)を語源にマレー、デンマーク、イタリアでテー(TE)、オランダ、フランスでは同じテーでも(THE)、そしてイギリスのティー(TEA)となりました。
一方、広東系の発音を語源にしたチャ(CHA)からスタートして、日本、ポルトガル、インドまでが同じ発音でチャとして残り、アラビア、トルコ、ロシアへはチャイ(CHAI)として広がりました。
そう考えると、ミャンマーでのお茶の呼び方をレテペというのも独特です。
茶葉の東洋医学的な効能は、キョ風(風邪を取り去る)、清爽頭目(頭や目の熱を取る)、清熱降火(熱を冷まし下に降ろす)、解暑、解熱毒、止痢、利水です。
ちなみに、腎陽虚(五臓六腑の腎の陽の働きが悪い)、脾胃虚寒(五臓六腑の脾胃が冷えて働きが悪い)タイプの人は控えたほうが良いです。
漢字で見た陰陽五行(2012年2月)
今回は東洋医学の基本概念である陰陽五行のそれぞれの漢字を手元の辞典(『漢辞海』三省堂)で調べてみました。
陰
日差しからかげになる側。山の北側。きた。川の南側。みなみ。くもり。黒くたちこめた雲。かげ。背面。男女(特に女性)の生殖器の通称。時間。年月。月。中国古代哲学の概念。姓。
『説文解字』形声文字で、門を閉じて暗いさま。川の南岸、山の北側。「こざとへん(=おか)」から構成され右の部分が音をあらわす。
陽
日なた。日のあたる側。山の南側。みなみ。川や湖の北側。きた。太陽。日の光。ひ。中国の古代哲学の概念。男性の生殖器。地名。姓。
『説文解字』形声文字で、高い。明るい。「こざとへん(=おか)」から構成され右の部分が音をあらわす。
五
数の名。いつ。いつつ。五回という度数。何度も。再三。いつたび。第五番目という序数。五倍。中国の民族音楽の音符の一つ。姓。
『説文解字』指事文字で、五行である。「二(=天地)」から構成され、陰陽が天地の間において交わるのである。
行
ゆく。いく。歩く。去ってゆく。離れてゆく。おもむく。出かける。流れる。(年月が)経過する。経る。おこなう。従事する。実行する。やってしまう。する。なす。使用する。採用する。広まる。流布する。運行する。めぐる。
『説文解字』会意文字で、人の歩きや走り。(ゆく)と(行きつもどりつする)から構成される。
陰も陽も五も行もすでによく知っている漢字ですが改めて辞書で調べてみると新しい発見があったりして面白いです。
山の北側が陰で南側が陽、川の北側が陽で南側が陰とそれぞれ山と川で陰陽が相対していて、陰陽それぞれが北と南の意味をもっているのも面白いです。
これは比較する相手や条件によって陰陽は変わるという陰陽の一つの特性をここからも知ることができます。
昔気功を習っていたとき中国人の気功の先生が、太陽と月を比較すると太陽が陽で月が陰、でも月と星を比較すると月が陽で星が陰になると言ってました。
五という字そのものに陰陽が天地の間において交わるという、この世界そのものの在りようが表されています。
行は季節や天体が運行する・めぐるという意味があり。
五行は世界というものは天地の間において陰陽が交わるということがずっとめぐっているということを示している。
五行そのものに陰陽が前提として含まれている。
そうすると陰陽五行といっても陰陽が中心なのだろうか?
色々考えると面白いです。
2012年新年のご挨拶 ~江戸しぐさ~(2012年年始)
新年あけましておめでとうございます!
今年も無事に新年を迎えることが出来ました!これもひとえに、患者さん、家族、友人など応援していただいている皆様方のお蔭です。
今後も鍼灸を中心に伝統の文化・技術を学ぶことにより自分自身を磨き、少しでも皆様方にお返しができればと思っています。
みなさんは「江戸しぐさ」をご存知でしょうか?公共広告機構のCMでも紹介されましたが、江戸しぐさは江戸の町人を中心とした生活の知恵・行動哲学です。
例えば「傘かしげ」、雨の中通りですれ違う時、お互いに傘を人のいない外側にかしげてお互いに濡れないようにすれ違うしぐさです。
江戸しぐさの根底に流れる思想は、お互いに気持ち良く世の中で生活をしていく、いわば共生の思想と、その為に自分自身やお互いを高めていく、磨いていく、人物を作るという思想です。
混迷の現代日本、人物を増やしていくことが必要です。
私も自分自身を磨き、一隅を照らしていきたいと思います。
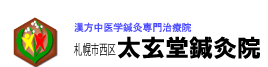
 院長の独り言メニューへ戻る
院長の独り言メニューへ戻る 院長の独り言メニューへ戻る
院長の独り言メニューへ戻る