「院長の独り言」年度別
2013年7月~12月の「院長の独り言」
- 湧泉(2013年12月)
- 百会(2013年11月)
- 『ガイアの夜明け』を観て、伝統の素晴らしさを思う(2013年10月)
- 秋の味覚(2013年9月)
- 『立川流鎖国論』(立川志らく著、梧桐書院)(2013年8月)
- 祖母を偲ぶ(2013年7月)
湧泉(2013年12月)
湧泉(ゆうせん)は足底にあるツボです。
天人地で分けた時、人の中で最も天に近いツボが百会だとしたら、もっとも地に近いツボがこの湧泉です。
泉の水が湧き出るように、五行の水に属する腎の経絡の気が初めて出る処なのでこの名がつきました。
湧泉には地衝や足心という別名もあります。
東洋医学的には「調腎気」、「利血脈」、「益腎滋陰」、「引火下行」、「平衝降逆」、「開竅啓閉」、「醒脳蘇厥」などの働きがあります。
具体的な症状としては、小児のひきつけ、てんかん、中風、人事不省、頭項痛、眩暈、耳鳴り、耳聾、舌本強、歯痛、小便不利、遺尿、水腫、遺精、不孕、心煩、心痛、心中熱、咳嗽、喀血、足膝冷痛、足心痛、奔豚気などがあります。
私の師匠が厥症(人事不省)のとき湧泉のツボを揉むのも救急の場合の方法のひとつと言っていました。
参考文献:『百穴精解』天津科学技術出版社
 | 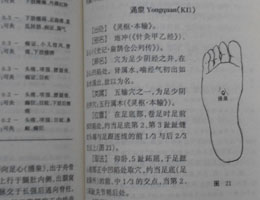 |
百会(2013年11月)
百会(ひゃくえ)というツボがあります。
百会は頭頂にあるツボで、「百」は「もろもろ」 、「会」は「あう」で、「もろもろのものが会うところ」が名前の意味となります。
具体的には手足の三陽経脈、督脈、足厥陰脈の交わるところです。
ちなみに百会には三陽五会、頂上、巓上、維会、五会、天満、三陽、白会などの別名もあります。
百会は東洋医学的には「活血通絡止痛」、「昇陽益気」、「熄風潜陽」、「キョ風散邪」、「醒脳」、「通督解痙」などの働きがあります。
百会は名前からも重要なツボだということが分かりますね。
実は、犬、猫、牛、馬などの動物にも経絡があり、百会というツボがあります。
動物の場合は人間の場合とは違い、腰のあたりに百会のツボがあります。
私の師匠は、冗談交じりに「本能」と「煩悩」の違いだと言っていましたが、進化によって脳が大きく発達した人間とその他の動物との相違ということでしょう。
動物の経絡が研究されていることも面白いですが、人間にも動物にも百会という同じ名前のツボがあり、しかもそれが異なる場所にあるというのも面白いですね。
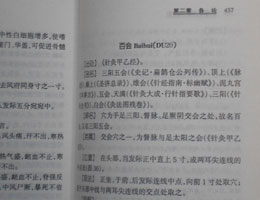 |
『ガイアの夜明け』を観て、伝統の素晴らしさを思う(2013年10月)
10月8日放送の『ガイアの夜明け』を観ました。
毎週この番組を観ているわけではないのですが、今回は「世界が絶賛!職人が生んだ驚きの新商品」というタイトルで、鍼灸という日本の伝統文化・技術を学んでいる者として興味深く拝見しました。
番組の内容としては、古くから伝わる伝統工芸が日本各地にたくさんありますが、現代において大変厳しい状況の産業も多々あります。そんな中伝統の技術を生かし頑張っている職人たちがいるという話です。
紹介されていたのは、初めは滋賀県大津市の桶職人中川周士さん(「中川木工芸比良工房」)。高級シャンパンの「ドン・ぺリニヨン」が絶賛した結露ができにくい木製のシャンパンクーラー。
次に福井県越前市の刃物工場「龍泉刃物」のすごい切れ味のステーキナイフ。 最後は石川県七尾市の「天池合繊」という会社の「天女の羽衣」という絹の4分の1の軽さで、髪の毛のおよそ6分の1の細さの糸で作った生地。
どれも素晴らしいものでしたが、それぞれの製品が生まれた背景に伝統の技術があったからこそということに感動しました。
やはり、伝統は素晴らしい。
翻って、我々鍼灸も東洋医学という伝統によって生まれました。
現代医学的な鍼灸をされる先生もいますが、五臓六腑・経絡という身体のバランスを整える鍼灸というのが、本来の鍼灸、東洋医学の鍼灸だと思います。
東洋医学というと一般の方は漢方薬を先ず思い浮かべられるでしょうが、東洋医学のもうひとつの大きな柱である鍼灸をもっと知ってもらい、もっと活用してもらいたいと番組を観て改めて思いました。
秋の味覚(2013年9月)
9月になり季節としては秋になりました。
秋は“味覚の秋”とも言われ、美味しいものが沢山ありますね。
ちょっと思いつくだけでも、栗、梨、柿、林檎(りんご)、葡萄(ぶどう)、などがあります。
ちなみに東洋医学では次のような効能があると言われています。
| 気味(性質) | 主治(主な働き) | |
|---|---|---|
| 栗 | 鹹、温、無毒 | 気を増やし、胃腸を厚くし、腎を補い、飢えに耐えれるようにするなど |
| 梨 | 甘、微酸、寒、無毒
※ただし食べ過ぎると冷やしすぎる、血虚の人も食べてはいけない |
熱による咳や渇きを止める、大小便の出をよくする、胸中の熱を取る、肺を潤す、酒毒をとるなど |
| 柿 | 甘、寒、渋、無毒 | 耳鼻の気を通じさせる、胃腸の不足を治す、酒毒を解く、口の乾きを止めるなど |
| 林檎 | 酸、甘、温、無毒 | 気を降ろし、痰を消す、霍乱による腹痛を治す、消渇の人はこれをよく食べるとよいなど |
| 葡萄 | 甘、平、渋、無毒 | 筋骨の湿によるしびれ痛み、気を増し力を強くする、飢えや風寒に耐えれるようになる、小便の出をよくする、面白いのは長く服用していると長生きとアンチエイジングによい、葡萄酒もよいとされる。 |
秋の味覚それぞれに効能があり、それを知るというのも楽しいことです。
参考文献
『本草綱目』
『立川流鎖国論』(2013年8月)
『立川流鎖国論』(立川志らく著、梧桐書院)の著者である立川志らくさんの祖父は、灸の名人として有名な深谷伊三郎さんです。
本書は師である立川談志や兄弟弟子や自分の修業時代や仕事に関して綴った内容のものです。
鎖国論というちょっと刺激的なタイトルですが、立川談志が落語協会を飛び出したあと立川一門は寄席に出られなくなりました。
かっては落語家は寄席が主要な活躍の場で、特に経験の浅い新人には大事な修業の場でたくさんの落語家を観て学ぶものだったのが、立川一門は師である立川談志と兄弟子しか観れないいわば鎖国状態でした。
そんな鎖国状態の中から志の輔、談春、志らく、談笑のように才能のある人材がでました。
本書での鎖国は要約するとそういうことで、「傑出した文化は鎖国から生まれる」とも書かれています。
考えてみると鎖国をした江戸時代は歌舞伎(かぶき)、浄瑠璃(じょうるり)、浮世絵(うきよえ)などの日本にしかない独特の文化が花開きました。
国家における鎖国か開国かは、その時代の国内情勢や世界情勢によって鎖国、開国のそれぞれのメリット、デメリットを勘案しながら考えるべきものでしょうが、落語と鍼灸で世界は違いますが弟子にとっては修業時代にいっとき鎖国状態になることが大切だと思います。
修業時代の鎖国とは師匠に染まりきることです。
本書では「師匠との価値観の共有」と書かれてますが、価値観を共有できなかった人は消えていき、共有できた人が残っていく、そういう世界なのでしょう。
価値観の共有といっても師と全く同じになれるわけもなく、本書で書かれていますが、談志と全く違うアプローチで師匠越えを狙うのが志の輔・談笑、談志の古典落語の美学・テクニックの部分でぶつかっていったのが談春、談志の了見・感覚の部分でぶつかっていったのが志らくということになるのでしょう。
志らくさんは談志師匠の影響で懐メロがの大ファンになり、映画やミュージカルもだいぶ影響を受けたそうです。
師と弟子について考えさせられる一冊でした。
祖母を偲ぶ(2013年7月)
個人的なことですが、私の祖母が先月、6月13日に亡くなりました。
94歳でした。
私は祖母に育てられたところもあるので、感慨深いものがあります。
生前祖母は延命処置を希望し無かったので点滴などはしましたが、過度な延命処置はしませんでした。
「今までは 生くべき時に 生きたれば 死ぬべき時に 死にて行くなり」
という歌がありますが、
自然のまま生き、自然のまま亡くなりました。
あるがまま、自然のまま
まさに、柳緑花紅
祖母は安らかで笑顔のように見えました
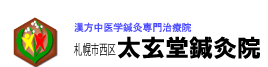
 院長の独り言メニューへ戻る
院長の独り言メニューへ戻る 院長の独り言メニューへ戻る
院長の独り言メニューへ戻る