「院長の独り言」年度別
2015年7月~12月の「院長の独り言」
- 『安藤昌益の自然哲学と医学 ―続・論考 安藤昌益〈上〉』(寺尾 五郎著、農山漁村文化協会)(2015年12月)
- 『江戸時代の医学 ―名医たちの三〇〇年』(青木歳幸著、吉川弘文館)(2015年11月)
- 『江戸時代の医師修業 ―学問・学統・遊学―』(海原亮著、吉川弘文館)(2015年10月)
- 漢方薬の保険適用外の動き(2015年9月)
- 『体の中の原始信号』(間中 喜雄、板谷 和子著、地湧社)(2015年8月)
- 『匂いの身体論』(鈴木隆著、八坂書房)(2015年7月)
『安藤昌益の自然哲学と医学 続・論考 安藤昌益〈上〉』(2015年12月)
本書『安藤昌益の自然哲学と医学 ―続・論考 安藤昌益〈上〉』(寺尾五郎著、農山漁村文化協会)は、天地を転定と書き改めたり、男女と書いてヒトと読ませたり、江戸時代の独創的な思想家安藤昌益について書かれた本です。
安藤昌益は武士や僧侶などの特権階級を無くして万民直耕を唱えたため彼の社会思想の面がよく語られますが、安藤昌益は実は医師でもありました。
本書ではそんな安藤昌益の自然哲学と医学の面について書かれています。
面白いのは安藤昌益の自然哲学と医学もかなり独創的なことです。
当時の医学の基礎となる自然哲学は気・陰陽五行で多くは説明されていました。
安藤昌益は自然の働きを「活真」、陰陽に相当するものを「進退」、木を「小進」、火を「大進」、金を「小退」、水を「大退」と呼び、土は活真そのもの、又は活真の行われる場として考え活真を「土活真」とも呼びました。
ここで安藤昌益は何故このように変えたのかと考えると、自然の働きはダイナミズムなのだという思いがあったのだと思います。
医学についても通常は外邪としては、風寒暑湿燥火の六邪ですが、安藤昌益は進木気は風邪で胆を傷る、退木気は滋邪で肝を傷る、進金気は涼邪で大腸を傷る、退金気は燥邪で肺を傷る、進火気は熱邪で小腸を傷る、退火気は蒸邪で心を傷る、進水気は寒邪で膀胱を傷る、退水気は湿邪で腎を傷ると八邪説となっています。
また互性という考えがあり、心と肺、大腸と小腸、肝と腎、胆と膀胱がそれぞれ互性の関係で、例えば心が病めば互性関係の肺も一緒に治療するというものでした。
昌益の医学の体系も独創的です。
安藤昌益の医学では婦人門(産婦人科)から始まり小児門(小児科)、頭面門(眼科・歯科・耳鼻咽喉科)、精道門(泌尿器科)、風門・滋門・熱門・蒸門・涼門・燥門・寒門・湿門(内科)、瘡門(外科)、乱神病(精神科)となります。
当時は本道(内科)から始まり、外科、眼科・歯科・耳鼻咽喉科、婦人科、小児科という流れが普通でした。
おそらく、その当時の医学を乗り越えようとした安藤昌益の苦闘なのだと思います。
実際には安藤昌益の医学は大きく広まることはありませんでした。
中央ではなく秋田という地方にいたことも関係しているかもしれません。
しかし、大正天皇をも治療した近代の漢方の名医浅田宗伯の『勿誤薬室方函・口訣』のなかに安藤昌益伝として安肝湯という小児の薬が載っているというのも面白いめぐりあわせだと思いました。
『江戸時代の医学 ―名医たちの三〇〇年』(2015年11月)
本書『江戸時代の医学 ―名医たちの三〇〇年』(青木歳幸著、吉川弘文館)は、名医達の話を中心にして江戸時代の医学、漢方・蘭方の全体像が述べられています。
個人的には石坂宗哲などは載っていましたが鍼灸の偉人達の話が少なかったのが残念でした。
面白かったのは躋寿館(後の幕府医学館)の医生を対象とした100日教育の内容です。
- 『本草』『霊枢』『素問』『難経』『傷寒論』『金匱要略』の六書を学ぶこと
- 経絡や穴処取りの技術を身につけること
- 止宿の者はこの間、門外他出を禁ずること
- 飲酒や勝負ごと、遊芸はもちろん、医学の助けにならざることは禁止のこと
- 止宿の者は自分賄い(自炊)すること
- 貧窮者には、名主や町役人らから証人や請人があれば、学館から食事や書物、夜具なども支給すること
- 禁制を破った者は、吟味のうえ、退去のこと
- 医学館での講説・会読の教授料は医学館から手当てするので、受講者からは一切徴収しないこと
以上の内容でその他、医案会、疑問会、薬品会なども行われていたそうです。
学ぶ者にとっては非常に恵まれた環境で、私も江戸時代の医生であれば是非とも参加したと思います。
『江戸時代の医師修業 ―学問・学統・遊学―』(2015年10月)
本書『江戸時代の医師修業 ―学問・学統・遊学―』(海原亮著、吉川弘文館)は、なかなか知り得ない江戸時代の医師の実像を知るひとつの手掛かりとして貴重な資料です。
江戸時代、医師になる多くは初め自分が住んでいる地域の手習い師匠から基礎的な教養を学び、その中の優秀なものが近隣の町や村の医師のもとに弟子入りし、そこで医学の基礎を学びました。
その後師匠の同意が得られると高度な技術を習うため近くの都市へ出向き、医学塾で鍛錬することになります。
さらには江戸・京都・大阪などの三都や長崎など医学の先進地へ修業の旅にいくこともあったそうです。
本書では実際の遊学の様子を、越前国福井藩府中領の医師皆川文中の日記や石渡宗伯の書簡から描き出していてとても面白かったです。
また福井藩の医学所のカリキュラムも資料から知り得て面白いです。
13歳になると医学所に入学し「萌生」となり、『小学』『四書五経』の素読をマスターし、漢方『傷寒論』『金匱要略』、蘭方『医範提綱』『解体新書』の習読が済んだ者は「初級」に進む。
「初級」は漢方『素問』『霊枢』『難経』『千金方』『同巽方』『外台秘要』『温疫論』『外科正宗』、蘭方『内科撰要』『熱病論』『病因精義』『医療正始』『済世三方』『和蘭薬鏡』『遠西名物考』『病学通論』等の習読が済んだ者、『傷寒論』『金匱要略』『医範提綱』についての詳しい講義を受けた者を「進業生」とする。
「進業生」のうち、毎年提出する「活按」で宜(優)が三年続いた者を「成業生」とする。ただし、原書の翻訳授講が出来る者は活按の成績に関わらず「成業生」とする。
「成業生」のうち受講の心がけがよく、学問・話術とも優秀な者を「得業生」と名付け、重役の医官として採用する。
このカリキュラムで面白いのは漢・蘭を等しく学んでいるという点です。
江戸時代、漢方医と蘭方医は一部では争いもあったのでしょうが、一般庶民への臨床の場では状況に応じて漢方や蘭方を使い分けて共存していたということが窺えます。
漢方薬の保険適用外の動き(2015年9月)
今年6月に財政制度等審議会が「財政健全化計画等に関する建議」を出しました。
そのなかで国民皆保険を維持するための公的保険給付範囲の見直しとして市販品類似薬等に関する内容もありました。
以下のとおりです。
「医療用医薬品については、使用実績があって、副作用の発生状況等からみて市販品としても適切であると認められれば、市販(スイッチ OTC)が認められる。これらについては、公平性の観点、セルフメディケーション推進の観点から、保険償還率をその他の医薬品よりも低くすべきである。さらに、長らく市販品として定着した OTC類似医薬品(シップ、目薬、ビタミン剤、うがい薬やいわゆる漢方薬などのうち長らく市販品として定着した銘柄)については公的保険から完全に除外すべきである。」
それを受けて政府の「骨太方針2015」でも、
「医療・介護提供体制の適正化、インセンティブ改革による生活習慣病の予防・介護予防、公的サービスの産業化の促進、負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化、薬価・調剤等の診療報酬に係る改革及び後発医薬品の使用促進を含む医薬品等に係る改革等に取り組む。」
となり、まだ正式に決まったわけではありませんが、漢方薬の保険適用外の可能性が出てきました。
医療費が年々増加していくなか、どこかを減らしていかなくてはならないのはしかたないのかもしれません。
漢方薬と鍼灸で業種は違いますが、同じく東洋医学を生業としている者としては残念です。
また、北海道は漢方生薬の産地でもあるので農家の方々への影響も心配です。
『体の中の原始信号』(2015年8月)
本書『体の中の原始信号―中国医学とX‐信号系』(間中 喜雄、板谷 和子著、地湧社)は1990年、今から25年前に出版されたものです。
著者の故間中喜雄先生は医師でありながら鍼灸業界の発展に寄与された大家です。
現在は鍼灸はまだそれ程でもないですが、医師が漢方薬を処方するのは当たり前の時代になりました。
しかし間中先生がご存命の頃は医師が漢方薬や鍼灸を行うのは、まだまだ変人扱いされた時代、そんな時代に医師でありながら鍼灸に情熱を傾けられたのは素晴らしいと思います。
もしかすると将来的には医師が鍼灸を行うのが珍しくない時代が来るかも知れません。
本書の内容としては、通常鍼の効果の説明は「鍼の刺激による反応を利用して治療する技術」とされていますが、刺激とは言えないほどの微小な謂わば信号によって身体が反応し変化する例をいくつか挙げ、その身体の反応をX-信号系と名付けて、経絡・ツボの身体反応もX-信号系によるものではないかという仮説を述べています。
微小な信号によって身体が反応する例として、メスメルの動物磁気説、フネケのインプレトール療法、ホメオパシー、O-リングテストなどが挙げられています。
またツボ・経絡が身体にどの様な反応をもたらすかの例に、いくつかの実験が述べられています。
実験1
○右手の合谷穴に圧痛があるとき、右手の曲池穴に電池のプラス極を当てると右手の合谷の圧痛が軽減する
○右手の合谷穴に圧痛があるとき、右手の曲池穴に電池のマイナス極を当てると右手の合谷の圧痛が増強する
○右手の合谷穴に圧痛があるとき、右手の二間穴に電池のプラス極を当てると右手の合谷の圧痛が増強する
○右手の合谷穴に圧痛があるとき、右手の二間穴に電池のマイナス極を当てると右手の合谷の圧痛が軽減する
実験2
○右手の魚際穴を赤色で塗ると右手の合谷穴の圧痛が軽減し、左手の合谷に圧通が現れる
○右手の少商穴を青色で塗ると右手の合谷穴の圧痛が軽減し、左手の合谷に圧通が現れる
これらの実験は直接的には臨床に役立たないかもしれませんが、ツボ・経絡が身体にどの様な反応をもたらすかという重要な知見を与えてくれるものと思います。
謂わば東洋的身体論のなかのツボ・経絡身体論というべきもので、西洋医学の基礎医学にも相当するものと思います。
このような分野も今後更に発展しなければならないと思いました。
『匂いの身体論』(2015年7月)
著者の鈴木隆氏は香料会社に勤務する調香師の方です。
本書『匂いの身体論―体臭と無臭志向』(鈴木隆著、八坂書房)は、汗や大便などの匂いの元となる成分の話から、フェロモンやムスク(麝香)などの香料の話、自己臭症の話、哺乳類の母子関係においても匂いが重要な役割をしており、人間においても分娩後一時間のうち母子の肌と肌の触れ合いが重要とされ、その時の匂いも関係しているようであるという話など匂いに関する話がたくさん書かれてます。
面白いのは歴史や文化によって匂いの意味づけが異なっているということです。
また本書のタイトルである「身体論」の説明に、
「近代西洋哲学において思考の対象から外されてきた人間の身体性という視点をもとに、もう一度人間とは何かを考えてみたものだろう。 身体論というジャンルが哲学史のなかに確固たるものとしてあるわけではなく、哲学、社会学、文化人類学、歴史学といった分野から、ときに医学的あるいは生物学的な視点を含んでなされた、身体をめぐるさまざまな考察が身体論の名で呼ばれている。」
と書かれており、
「その背景に西洋ではもともと歴史的に精神は高等で肉体は下等であるという心身二元論であり、それを明確にしたのがデカルトであり、その後精神のみを扱う哲学は主観的、観念的な方向に向かい、身体と物質を精神と切り離して客観的に扱う態度が近代科学へと向った。
この心身二元論に対立する一元論のものとして唯心論と唯物論があり、唯心論は精神が全てを作りだすというもので物質も精神の作りだす現象と捉え、唯物論は物質が全てを作りだすというもので突き詰めれば人間のからだは機械と同じとなる。
そのような背景の中で心身二元論の伝統のもとでは身体そのものが蔑視され、また唯物論的な一元論では人間は機械という見方に行き着き、機械と世界の接点である感覚に関心が向いたものの臭覚はあまり研究の対象となっていない」
とし、これまで嗅覚が重要視されなかったのは何故かという文化的背景から問い直し嗅覚、匂いというものの意味を改めて問い直し人間というものを考えようということが筆者のいう「匂いの身体論」と思われます。
この身体論というものがここ近年出てきたことに、私は非常に共感を覚えます。
今迄と違った視点から身体を見ると、これまでとは異なった様相の身体が見えてきたりします。
そのような多元的な身体を知る一助に東洋医学的な身体観もあると思います。
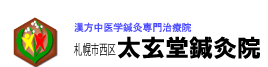
 院長の独り言メニューへ戻る
院長の独り言メニューへ戻る 院長の独り言メニューへ戻る
院長の独り言メニューへ戻る