「院長の独り言」年度別
2016年1月~6月の「院長の独り言」
- 張仲景(2016年6月)
- 前漢の名医 太倉公・淳于意(『中医趣談』より)(2016年5月)
- 中国医学の祖 黄帝(『中医趣談』より)(2016年4月)
- 『茶の湯と陰陽五行』(淡交社編集局編集、淡交社)(2016年3月)
- 『医者は現場でどう考えるか』(ジェローム・グループマン著、美沢 惠子訳、石風社)(2016年2月)
- 戦のない世を目指して ~戦国スーパードクター 曲直瀬道三~(2016年1月)
- 2016年年始のご挨拶 ~大病を小病に、小病を無病に~(2016年年始)
張仲景(2016年6月)
張仲景、名は機、仲景は字、後漢の終わり頃、南郡涅陽(今の河南省南陽県)の人、仕官して長沙の太守となります。
張仲景は青年の頃、同郷の張伯祖より医学を学びました。
張仲景の一族は二百人余りいましたが、そのうちの三分の二が亡くなりました。
亡くなった人の七割は傷寒病(伝染性の急性熱病)でした。
そのため張仲景は医学の研鑽を重ね、後に『傷寒雑病論』を著します。
張仲景の著した『傷寒雑病論』(『傷寒卒病論』ともいう)は中国医学において非常に重要な役割を果たしました。
一言で言うと『傷寒雑病論』は『黄帝内経』の基礎理論を継承、発展させて弁証論治の基礎を作りました。
そんな『傷寒雑病論』ですが戦乱などで散失します。
その後、傷寒の部分は晋の時代の王叔和、唐の孫思バクなどにより散失した部分が収集され、宋の時代に林億らによって正式に『傷寒論』として出版されます。
雑病の部分も孫思バク、王洙などにより収集され、宋の時代に『金匱要略』として刊行されました。
そんな張仲景は後世では医聖と称され、伝説的な話もいくつかあります。
次の話は『鍼灸甲乙経』の序文にも載っている話で、内容はこうです。
張仲景と20代の王桀(字仲宣)が会ったとき、「王さん、貴方は病気だ、もし五石湯を服用すれば、病根を取り除くことも可能だ、そうしないと40歳前後で眉が落ち、生命の心配もある。」と張仲景は言った。
王桀はその話を不愉快に思い、薬を飲まなかった。
その後しばらくしてから二人が再び会い、張仲景が王桀に薬を飲んだか聞いた。
王桀は「もうすでに飲んだ」とうそを言った。
張仲景は「気色を見れば、薬を飲んでない様子が分かる。君は何で命を軽んじるのだ。」と言った。
王桀は何も言わなかった。
その後、不惑の年になったとき、果せるかな眉毛が脱落し、だいたい半年ほどで張仲景の言った通り亡くなった。
張仲景の医聖と呼ばれるのに相応しい伝説ですね。
参考文献
『中医趣談』(広西師範大学出版部)
『中国医学の歴史』(伝 維康、 呉 鴻洲 編、川井 正久、山本 恒久、川合 重孝 訳、東洋学術出版)
前漢の名医 太倉公・淳于意(『中医趣談』より)(2016年5月)
今回は太倉公・淳于意について、前回同様『中医趣談』(広西師範大学出版部)を参考に紹介したいと思います。
淳于意は前漢で唯一名医として正史に出てくる。かつて斉の国の倉庫の役人・太倉長だったので、後の人は彼のことを倉公或は太倉公と称した。
彼は若い時公孫光門下の学医の下に身を投じた。
後に公乗陽慶師のところに投じ、多くのことを専門に修め、尽くその真伝を得た。
公乗陽慶は大切に保管していた黄帝や扁鵲の書を淳于意に伝えて助けた。
この時、淳于意の医道、医術はすでに成熟しており、彼は病を診るのによく五色(望診)を用いた。そのうえ人の生死(病の予後)がよく分かった。
テイエイ父を救うは『史記』に記載され人口に膾炙されている故事である。淳于意は勢力のある貴族の病を診るのを断った為無実の罪で訴えられた。漢の文帝十三年捕えられ投獄され、判決で足を切られる刑となる。
淳于意の娘のテイエイは父に随って長安の都に来た。文帝に上書し、自分を罰として国の奴婢にする代わりに父親の罪を赦してくださいといった。
文帝は少女の孝行に尽くす姿と大胆にも上書する勇気に感動して、特別に淳于意を釈放した。
診籍(カルテ)は倉公淳于意によって初めて創られた。
彼が漢の文帝の召見を受け入れた時、詳細に25の症例を紹介した。一つの症例ごとに病人の姓名、性別、職業、居留地、病理、診断、治療、予後状況等詳細に紹介した。これは文献として最も早く見られるカルテである。
25例のカルテのなか淳于意の望診が優れているのを反映している例が数例ある。
斉の宰相の家人の如きは自分では病気を自覚していなかった、しかし淳于意は望診で色を診て病気があるのが分かった。望診すると殺然とした黄色が診られ、死青が増えていくのが察せられた、これは脾気が傷られ、まさに春に至っては膈が塞がり気が通ぜず、飲食が能わず、夏に至っては下血し死すだろう。
その後、家人は次の年の春に病を得、夏に入ると下血し亡くなった。
淳于意は脈診にとりわけ精通していた。25の症例中10例は脈診によって診断された.斉の国の淳于司馬が病に罹った。多くの医師は死症と断じた。淳于意はこの脈を診て、この病は順証で治ると診た。火剤を米のとぎ汁で飲ますと病は癒えた。
淳于意の人柄は控えめで誠実、だが飾らないところが短所である。
漢の文帝がかって淳于意に聞いた。「病を診て死生を決す(予後を判断する)のに全く失敗が無くできるか」と。彼は答えて言った。「時々失敗する。私は全て出来るということは無いと思う」と。
(『中医趣談』「太倉公」より引用。福田訳)
中国医学の祖 黄帝(『中医趣談』より)(2016年4月)
今回は中国医学の祖とされる黄帝について『中医趣談』(広西師範大学出版部)を参考に紹介したいと思います。
黄帝は伝説では中国の夏族の祖先であり、古代中国医学の鼻祖である。
彼は有熊一族の少典の子で、姓は姫、姫水(現在の陜西省内)で生まれ育った。
伝説では黄帝は竜顔(君子の容貌)を持ち聖人の徳があり、生れながらにして良くものを話し、天下万物全ての事に秀でていた。
彼は長江の南や北、黄河の上流や下流など様々な所へ行き、師を探しては学んだ。
東は青丘へ行って紫府先生に会って万神に効のある三皇天文を授けられ、具茨へ行って大隗君に会って神芝図を授けられ、蓋上へ行って中皇真人に会って九茄散を授けられ、羅霍へ行き黄蓋童子に会い金銀十九帖を授けられ、コウドウへ行き広成子に会い自然経を授けられた、峨眉山を訪れ黄君に会い真一経を授けられた、金谷に入り導引養生について問い玄素二女の著作について聞いた。
身近にいる医学に詳しい雷公、岐伯、伯高、少兪などの経験を集め終に脈書を成す、またその他に難しい問題を一通り問い内外十八巻の即ち『黄帝内経』を書いた。
かって王屋山に登った時、宮門の下で三日斎戒をし宮門を登っていくと、うつくしい林があり玄女九鼎丹を得る幸運があった。
また茅山で銅を煮た薬を採ったり、荊山の千鼎湖の上に煉丹の炉を建てた。(『中医趣談』「国医之祖」より引用。福田訳)
上記のとおり黄帝は伝説上のヒーローです。
司馬遷の『史記』の一番最初、五帝本紀も黄帝の話から始まります。
中国の歴史上、東洋医学以外の分野にも、黄帝の名の着いた書物がたくさんあります。
それだけ多くの人が黄帝に想いを託して書物を書いたのでしょう。
『黄帝内経』も黄帝に想いを託したそんな本の中の一冊なのだと思います。
『茶の湯と陰陽五行』(2016年3月)
東洋医学の基礎となる陰陽五行思想は、日本の文化にさまざまな影響を与えました。
本書『茶の湯と陰陽五行―茶道具にみられる陰陽五行』(淡交社編集局編集、淡交社)では茶の湯と陰陽五行思想の関係がいくつか紹介されています。
たとえば、寅の刻に水を汲むのは木火土金水のなかの木気に一日のうちで最初になる時刻で季節でいえば春に相当し陽気が生れる時なので水を汲むのに適した時間であります。
五行棚には文字通り竹(木)の柱、炭の火、風炉の土、釜の金、水の五行が揃っています。
また茶事は初座は陰、後座は陽とそれで陰陽が揃うようになっています。
東洋医学には、天人合一という言葉があり、大宇宙と小宇宙(人体)は相関しているというものです。
同じように茶道においても、四畳半ほどの小さな空間のなかで茶を服するという行為のなかにも世界(宇宙)が在るということなのでしょう。
それを表現するのに、謂わば陰陽五行という記号で表しているのだと思います。
私は茶道に関しては全くの門外漢ですが、陰陽五行思想がこのように使われていると知ると面白くまた嬉しく思いました。
『医者は現場でどう考えるか』(2016年2月)
本書『医者は現場でどう考えるか』(ジェローム・グループマン著、美沢 惠子訳、石風社)の著者ジェローム・グループマン氏は、ハーバード大学医学部教授で、がん、血液疾患、エイズ治療の第一人者であり、多くの新聞や科学雑誌に寄稿している方です。
本書は一般の方を対象として書かれており、分かりやすくしかも本質的なことが書かれています。
アメリカの医科大学教育において近年は、アルゴリズムやディヴィジョンツリーなどの論理的診断や科学的エビデンス(統計学的に立証されたデーターに基づいた治療)が重要視されています。
しかし、著者はそれを評価しつつ、ある種の危惧も抱いています。
論理的思考による診断だけでなく、パターン認識などによる直観的認識や自分自身で考えたり、創造的に考えることも大事なのではないか。
統計は平均を表すもので必ずしも個体を表していない、また医師個人の経験に基づく知恵(臨床試験の成績から得られたベストの治療法が、目の前のその患者のニーズや価値観に適合するかどうかを判断する医師個人の知識)も大切なのではないか。
また著者は、実際の現場についても述べています。
実際の現場の医師は膨大なデーターを集めてからありうる診断に悠長に仮説をたてて考えるようなことはしない、患者に会った瞬間から診断を考え始めなければならない。
誤診の大半は技術的な問題ではなく、医師の思考法の欠陥(いわば思考の落とし穴)によるものである。
本書ではいくつか例え話も出てきてそれも面白かったです。
見た目はアヒル、歩き方はアヒル、鳴き声はアヒルの動物はなんだ?
答えはアヒル。
ところが、いつもアヒルとは限らない。
本書を読み終わった後、思い浮かんだのは将棋や囲碁の棋士の話でした。
プロの棋士は、対局のとき直観的に最初に頭に浮かぶ手が8~9割正解だそうです。
それまでの経験からその局面がパターンとして類型化され、認識され、それが直観的に把握されます。
あとはそれに誤りがないか、見落としがないかどうかを確認するのに時間が必要なのだそうです。
私たち東洋医学では弁証論治という論理的なアプローチも持ちながら、直観的なアプローチも持っています。
双方の良い点を補いながら、より良い治療に繋げていけたらと思います。
戦のない世を目指して ~戦国スーパードクター 曲直瀬道三~(2016年1月)
1月13日(水)にNHKで放送された歴史秘話ヒストリアは「戦のない世を目指して ~戦国スーパードクター 曲直瀬道三~」と題して 曲直瀬道三についてでした。
曲直瀬道三は日本漢方のなかの後世派というとても大きな流れを作った名医です。
日本漢方の流れとしては後世派のほかに古方派、折衷派などがあります。
歴史秘話ヒストリアのなかでは、師である田代三喜との出会い、毛利元就の治療、弟子の施薬院全宗との関係などをドラマ仕立てで、文字通りドラマチックに描いていました。
番組ではでていませんでしたが、田代三喜はその当時の中国である明に渡り、明で李朱医学を学び、それを日本に持ち帰っています。
また曲直瀬道三がキリスト教に入信するのも単にキリスト教の博愛精神に共感しただけでなく、宣教師を通じて西洋の医学をも学び自身の医学を向上させたいという思いもあったようです。
曲直瀬道三が灸を多用したことから番組では、長野先生、谷岡先生など鍼灸師の先生が灸をしている場面なども映し出されていました。
曲直瀬道三の他にも日本には永田徳本、吉益東洞、後藤艮山などや、鍼灸の方では杉山和一、石坂宗哲などまだまだ興味深い名医達が沢山います。
今後も、もっともっと、多くの名医達が取り上げられるのを切に願います。
当記事関連サイト
今回の記事でご紹介した「戦のない世を目指して ~戦国スーパードクター 曲直瀬道三~」は、NHK歴史秘話ヒストリアの公式ウェブサイトのバックナンバーで確認することができます。詳しくは、「戦のない世を目指して ~戦国スーパードクター 曲直瀬道三~」をご参照ください。
2016年年始のご挨拶 ~大病を小病に、小病を無病に~(2016年年始)
あけましておめでとうございます。
本年も無事にお正月を迎えることができました。
これもひとえに太玄堂を支えてくださる皆様のお蔭だと思っております。
鍼灸は、大病を小病に、小病を無病にするものと思います。
少しでも皆様方の健康のお守りになれるように、本年も精進したいと思っています。
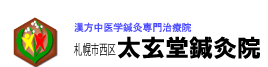
 院長の独り言メニューへ戻る
院長の独り言メニューへ戻る 院長の独り言メニューへ戻る
院長の独り言メニューへ戻る