「院長の独り言」年度別
2024年7月~12月の「院長の独り言」
- オ血に使用するツボ(2024年12月)
- 糖尿病(2024年11月)
- 高血圧(2024年10月)
- 『老子 その思想を読み尽くす』(池田知久著、講談社学術文庫)(2024年9月)
- 不眠(2024年8月)
- 便秘(2024年7月)
オ血に使用するツボ(2024年12月)
今回はオ血に対して使用するツボを幾つか簡単に説明します。
まず、三陰交、このツボは昔は女三里とも呼ばれ、血の道症(月経前症候群や更年期障害などの婦人科疾患)によく使われました。
血虚のときは補血としても使えます。
血に対するツボとしてはある意味オールマイティに使われるツボです。
次に血海、このツボは名前に血という字が付いているように血と深い関係があるツボです。
このツボも血を補うのにも使えます。
膈兪、このツボは八会穴のなかの血会となっており、このツボも血と関係が深く、補法にも瀉法にも使えます。
藤本先生は血に関係が深いツボとして、膈兪、血海、三陰交、公孫を重視されています。
あと、オ血に使用するツボとして臨泣を重視されています。
中医学のテキストでは、テキストによって多少異なりますが、心兪、次リョウ、百会などもオ血に対して有効なツボとされています。
参考文献
『経穴解説』(藤本連風著、メディカルユーコン)
『常用兪穴臨床発揮』(李世珍著、人民衛生出版社)
糖尿病(2024年11月)
今回は糖尿病について。
糖尿病は東洋医学では消渴病といいます。
消渴病は多飲、多食、多尿の三多の症状と、他にるい瘦、尿が甘いなどの症状があります。
『実用中医内科学』(上海科学技術出版社)では、
・肺胃燥熱
・腸燥津傷
・肝腎陰虚
・陰陽両虧
・脾胃気虚
・湿熱中阻
以上のように分けています。
実は東洋医学の理論的な分析はテキストにより多少異なります。
『中医内科』(金剛出版)では、
上消(肺が中心):多飲、口渇
中消(胃が中心):多飲、多食、るい瘦
下消(腎が中心):多尿、頻尿
と分けています。
いづれにせよ、熱邪、燥邪がカギとなるように思います。
高血圧(2024年10月)
今回は高血圧について、簡単に述べます。
高血圧は血圧計による測定で140/90mmHg(自宅での測定の場合は135/85mmHg)以上の状態と定義されています。
年齢にかかわらずこの数値が基準となりますが、一般的に年齢を経ると血圧は上がりますので、20代と60代が同じ基準というのは厳しすぎるのではないか、上の血圧(収縮期血圧)は年齢+90ぐらいを基準にしてもいいのではないかという意見もあるようです。
東洋医学では高血圧をどう考えるかということですが、残念ながら東洋医学では高血圧という概念がありません。
東洋医学は機械を使わず五感を大事にしています、そのメリット、デメリット両方あると思いますが、ここではそれは置いておいて、では東洋医学では高血圧をどう考えるのか?
一つの考え方として、症状から論理的に考えるアプローチがあります。
高血圧のよくみられる症状として、頭痛やめまいがあります。
頭痛もめまいも東洋医学的に分析されています。
頭痛:風寒、風熱、風湿、肝陽、気虚、血虚、腎虚、痰濁、オ血など
めまい:肝陽上亢、気血虧虚、腎精不足、痰濁内蘊、オ血阻絡など
以上から肝火、痰熱、腎虚などが深く関係しているといえると思います。
よって高血圧は主に肝鬱化火タイプ、痰湿中阻タイプ、陰虚陽亢タイプと分けることが出来ると思われます。
もう一つは脈やツボの状態などから導き出すアプローチがあります。
具体的に説明するのは難しいのですが、経験的に高血圧の方は肝、腎、気逆、熱邪、痰湿が関係することが多いと思います。
どちらのアプローチからでも、だいたい同じ結論にたどり着きます。
『老子 その思想を読み尽くす』(2024年9月)
本書『老子 その思想を読み尽くす』(池田知久著、講談社学術文庫)は『老子』の解説書ですが、私達が通常目にする通行本の『老子』だけではなく、それよりも古い馬王堆帛書の『老子』甲本と乙本、郭店楚墓竹簡の『老子』甲本と乙本と丙本、北京大学竹簡の『老子』も参考にし、その他『荘子』や『淮南子』などの道家の書や『呂氏春秋』などに引用された道家の文章などから『老子』の書を読み解こうとするものです。
古い『老子』は通行本の『老子』と比べて、分量が少なかったり、異なるところがあったりして『老子』は中国戦国時代後期から前漢初期にかけて成立したものであるということ。
他の書物の文章や『老子』の文章における言葉の使われ方から、同じ言葉でも意味合いが違っているということ、特に「自然」という言葉の使い方の違いから『老子』が古い道家の思想とその当時の新しい道家の思想が混在しているということ。
道器論(道(形而上の目に見えない万物の根源や働き)と器(形而下の目に見える万物)の関係性)が『老子』の重要なテーマの一つであると思われるが、そこから派生して聖人の無為自然が述べられ、無為(道)と自然の関係性が変化し、新しい道家の思想では自然の方にウエイトがシフトしているということ。
等々本書を読んで非常に面白かったです。
話は脱線しますが、私は子供の頃から『老子』に非常に惹かれました。
何でそんなに惹かれるのか改めて考えてみました。
『戦争と平和』や『イワンのばか』などで知られるロシアの文豪トルストイですが、『老子』を非常に高く評価していました。
彼は『老子』のこれもまた重要なテーマの一つであると思われる不争・戦争の否定の教えに感銘を受けていたようです。
人によって、色んな読み方、色んな惹かれるポイントがあると思いますが、私は何で惹かれるのか? 二点ほど思い浮かびました。
一つは、逆説的な表現。
もう一つは、読後感が息苦しさが無くなる感じ。
逆説的な表現は、ことわざなどで多く使われます。
例えば「急がば回れ」、急いでいるのだから近道すればいいのにあえて遠回りせよ、これは慌てず着実な方法をとれということを逆説的に表現したもの。
読後感が息苦しさが無くなる感じ、というのは説明が難しいのですが、例として『老子』の中に「学を断てば憂いなし」とか「無知」を勧める文章があります。
この当時の学問・知というのは儒家の学・知であり、仁や礼といった儒家の価値観、儒家の正義によって世の中を変革しようというものでした。
現代でもそうですが、一つの価値観、一つの正義によって強制される世界はあまり居心地が良くありません。
武力にしろ、知・価値観にしろ、仮にそれが正しいものであっても強制されることは良くないと『老子』は謂っているように私には思えてなりません。
不眠(2024年8月)
今回は不眠について、東洋医学的な説明を簡単にではありますがしてみます。
不眠の原因としては、ストレスなどによる情志の失調、心労が続いたり出血などによる血虚、陰虚、邪熱、心気虚、飲食の不摂生などによる胃の不調和など様々あり、東洋医学では、以下のように分類しています。
心脾両虚:過度の心労、産後の失血、手術後の衰弱、高齢などによる気血不足により心神を養えずに不眠が起こる
陰虚火旺:心陰が不足することにより熱邪が生じ不眠が起こる
心腎不交:腎陰が損傷し心陰を助けれずに不眠が起こる
肝鬱血虚:ストレスなどによる情志の失調により肝が傷つき不眠が起こる
心虚胆怯:もともと心気が虚していて驚きやすく怖がりで心神が不安定のため不眠が起こる
痰熱内擾:痰熱が体の中に生じ心神を擾乱するために不眠が起こる
胃気不和:飲食の不摂生などによる胃気の不和により不眠が起こる
参考文献
『実用中医内科学』(上海科学技術出版社)
便秘(2024年7月)
今回は便秘について、東洋医学的な説明を簡単にではありますがしてみます。
まず便秘の原因として、熱邪によるもの、気の停滞によるもの、気や血や陰液の不足によるもの、寒邪によるものなどが考えられます。
それで、以下のように便秘のタイプを東洋医学(中医学)では分けています。
熱秘:熱邪が胃腸にこもることにより生じる便秘、そのため津液が損傷し大腸が乾燥する。
ツボとしては、合谷、曲池の鍼など。
気秘:ストレスや運動不足などにより気が停滞することにより生じる便秘。
ツボとしては、中カン、行間の鍼など。
虚秘:気虚便秘、血虚便秘、陰虚便秘の3種類に分かれるが、いづれにしても大腸の働きが低下することにより便秘が生じる。
ツボとしては、脾兪、胃兪の鍼など。
冷秘:身体を冷やす飲食物の摂りすぎや陽気の不足により寒邪が生じることにより起こる便秘。
ツボとしては、神闕、気海の灸など。
また、どのタイプの便秘に対しても大腸兪、天枢、支溝などのツボへの鍼も有効だと思います。
その他に便秘で著名なツボとしては、沢田流神門の灸、柳谷便秘穴など様々あります。
参考文献
『実用中医内科学』(上海科学技術出版社)
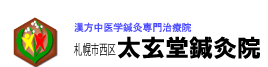
 院長の独り言メニューへ戻る
院長の独り言メニューへ戻る 院長の独り言メニューへ戻る
院長の独り言メニューへ戻る