「院長の独り言」ジャンル別
「院長の独り言」ジャンル別~鍼灸・漢方・東洋医学・東洋思想・気功編~
鍼灸・漢方・東洋医学・東洋思想・気功編 ―2008年-2010年―
- 東洋医学・伝統医学の意味(2010年12月)
- 『桂ちづる診察日録』(2010年9月)
- 静座(2010年6月)
- 八段錦(2010年5月)
- 爪について(2010年4月)
- 鍼の起源(2010年2月)
- 一寸法師は鍼灸師!?(2009年8月)
- カンフーと功夫(2009年7月)
- 鍼灸師も職人~勘・感覚を磨くことが大切~(2009年4月)
- 気について(2009年2月)
- 太陽人 イ・ジェマ ~韓国医学の父~(2008年9月)
- 散歩・逍遥と呼吸法、鍼治療で気の活性化を(2008年8月)
- 鍼と針(2008年6月)
- 桃太郎は金太郎?~昔話と東洋思想・五行説との関係~(2008年5月)
- 東洋医学・鍼灸医学を学ぶ効用~新年のご挨拶にかえて~(2008年1月)
東洋医学・伝統医学の意味(2010年12月)
本年もあと一ヶ月ほどとなり、無事に本年を終えることが出来そうです。
これもひとえに患者の皆様、友人、知人、家族など太玄堂鍼灸院を支えてくださった皆様方のお蔭だと感謝しております。
東洋医学・伝統医学に意味があるとすれば近・現代医学が見落とした「何か」があるからでしょう。
近・現代医学と東洋医学・伝統医学の一番大きな違いはダイナミックな躍動する生命のちからというものへの眼差しではないでしょうか。それは生命の力(自然治癒力)に対するロマンといってもいいかもしれません。
ヒポクラテスは病気は体の部分にあるのではなく体全体が病気になるとして病気を全体として捉えました。ヒポクラテスはそれを体液病理学説として表現しました。我々鍼灸師は気という概念でこれを捉えます。
現代のような固体病理学では病気は全体ではなく局在にあることになります。つまり病気は部分の問題で体全体つまり自然治癒力は関係ない。
その批判から現代では西洋医学はホリスティック医学を提唱しています。理念としては素晴らしく正しいことだと思います。しかしその視点での具体的かつ有効な手段を現代医学が生み出せているか疑問なところもあります。
我々鍼灸をはじめとした伝統医学・東洋医学はその有効な手段や思想を提供できるものだと思います。
NHK土曜時代劇 若き女医桂ちづるの物語『桂ちづる診察日録』(2010年9月)
今回は、NHK土曜時代劇の紹介です。タイトルは『桂ちづる診察日録』です。9月4日(土曜日)から、NHK総合で毎週土曜日の午後7時半から8時までの30分放送します。
原作は、『藍染袴お匙帖(あいぞめばかま おさじちょう)』(藤原緋沙子著、双葉文庫)、主演は、桂ちづる役で女優の市川由衣さん。
内容は江戸時代、江戸の神田に住む、蘭方医で華岡流外科も学び、亡き父に漢方も仕込まれた若き女医桂ちづるの日々の成長を描くというものです。
昨年TBS系列で、日曜日午後9時から『JIN -仁-』が放映されて人気でした。これは現代の外科医が江戸時代にタイムスリップするという話でした。私も面白くて毎週見ていました。
ただ、西洋医学のほうが東洋医学より勝っているというステレオタイプの内容が気になりました。
『JIN -仁-』の場合は仕方ないとしても『桂ちづる診察日録』の主人公も蘭方医で外科手術が得意ということで、東洋医学を行っている鍼灸師としては東洋医学が活躍する内容であってほしいとちょっと思います。
静座(2010年6月)
前回、八段錦という気功について書きました。
八段錦のように動作のある気功を動功といいます。
気功には動功と並ぶもう一つの大きな柱に静功というのがあります。
静功とは静座つまり座禅や瞑想と同じものです。
静座の効用はいろいろありますが、こころ・精神を落ち着かせるというのが一番の効用だと思います。
私も静座をするのですが雑念が多くて上手くいかないことも多いですが、スッと心が静かになる気持ちのいい時間を過ごせるときがあります。
ちなみに脳波にはベータ波(はっきりと起きている状態、13~30Hz)、アルファ波(リラックスしている状態、8~13Hz)、シータ波(深いリラックス・浅い眠り・瞑想状態、4~8Hz)、デルタ波(深い睡眠状態・深い瞑想状態、0~4Hz)の4種類があります。
本来は静功・瞑想は一般にリラックス状態として知られているアルファ波よりもっと深い状態を目指すものですがそこまでいかなくても十分に効果があると思います。
キリスト教徒だった新渡戸稲造も彼は黙思という言葉を使ってますが、一日一回は世間の喧騒から離れて黙思(静座・瞑想)することの大切さを説いていています。
八段錦(2010年5月)
最近、「八段錦」を習い始めました。
八段錦とは中国に古くから伝わる導引の一つで、導引とは簡単に言うと気功の一種で呼吸に合わせながら身体を伸ばす動作を行うものです。
実際にやってみると、見るのとやるのとでは大違いで結構大変です。
でも終わった後は非常に爽快感があり、鍼灸とはまた違った心地よさがあります。
導引は『荘子』の中にも熊や鳥の動作として紹介されています。
八段錦と並ぶ有名な導引に三国志にも出てくる有名な医者である華陀が作った「五禽戯(ごきんぎ)」という虎、鹿、熊、猿、鳥の動物の動きを真似た導引もあります。
導引の歴史も古く馬王堆(中国漢代のお墓)の中から導引をしている図が見つかっています。
馬王堆は私達、鍼灸師にとっても『陰陽十一脈経』や『足ひ十一脈経』など現在の十二経絡以前の十一経絡の古い文献等も出土しています。
『黄帝内経』の異法方宜論にはお灸は北の地方から鍼は南の地方から漢方薬は西の地方でから導引は中央の地方からへん石は東の地方から来たとされています。
現代においては鍼灸や漢方薬や導引は別々に使われていますが、古代においてはもっと身近にもっと合わさった総合的な形で使われたと思います。
爪について(2010年4月)
東洋医学は西洋医学と違い診断に機械を使いません。
そのため東洋医学では五感を駆使して身体のアンバランスを判断します。
その判断材料の一つに爪があります。
東洋医学では爪がもろく、つやがないのは血虚をあらわしていますし、どの指の爪に異常があるのかによってどの経絡の異常かを判断します。
当院の患者さんで若い時から喘息を患っているお婆さんがいるのですが、その方は親指の爪が他の指よりスジが多く白い色をしています。
(親指は肺の経絡が通っていますので、長く喘息の持病があるため肺の経絡に異常を起こしたものと思われます。)
お灸の名人だった深谷伊三郎先生の『お灸で病気を治した話』には白内障の予後の判定に爪を見て判断する話が載っていますが名人は独自に自分なりの判断方法を見つけ出すところに感心させられます。
指先が膨らんで太鼓のバチのような形になり、そのため爪が指先を包むように大きく丸くなるバチ指という症状があるのですが、これは別名ヒポクラテス指又はヒポクラテス爪といわれ古くから肺の病気と関係があることが知られています。
例えば肺がんを例にとると、肺に転移した転移性の肺がんの場合はあまり出ませんが肺から起こった原発性の肺がんの場合六割のひとにバチ指が見られるそうです。
爪一つとっても、奥が深いですね。
鍼治療の起源(2010年2月)
鍼治療の起源については実際のところよく解かっていません。
一般的には『中国医学の歴史』(東洋学術出版社)などに書かれているように「へん石」と呼ばれる石を加工した治療用具が鍼の起源だといわれています。
『素問医学の世界』(藤木俊郎著 績文堂)には入れ墨が鍼の起源ではないかという面白い説が載っています。
日本や中国で入れ墨は刑罰として使われた時期も有りますがそれ以前には別の意味合いがあったようです。
北海道のアイヌ民族や沖縄の人達が入れ墨をしていたことは知られていますが、縄文時代の土偶の文様も入れ墨ではないかと謂われています。
シベリアのコリャーク族は痛む部位にその痛みを追い払うために入れ墨をしたり、不妊に対するまじないで顔面に入れ墨をしたりしますそういったことから入れ墨から鍼が生まれたのではないかと述べています。
 1991年アルプスの氷河で見つかった約五千年前の男性のミイラ(アイスマン)にはちょうどツボの位置に入れ墨があるのが見つかっており、鍼治療の痕ではないかとも謂われています。
1991年アルプスの氷河で見つかった約五千年前の男性のミイラ(アイスマン)にはちょうどツボの位置に入れ墨があるのが見つかっており、鍼治療の痕ではないかとも謂われています。
私は個人的には入れ墨という行為そのものには否定的なのですが、鍼の起源として考えると面白いなと思います。
へん石は膿を出したり瀉血などに用いられるどちらかというとメスのような形で単に刺入する一般的な鍼とはすぐに結びつかない気もします。
(もちろん古代には九鍼といって、現在一般に使われる刺す鍼の他に膿を出したり瀉血の為に切り開く鍼や刺さないでツボを刺激する鍼などいろいろ有りましたから鍼の起源の一つの流れであることは間違いないとは思います。)
薬草を使った治療法は世界各地で生じていますが、鍼治療は他の地域には生まれず何故中国にだけ生まれたのか?私はずっと疑問でした。
入れ墨の文化は世界各地にありますので、もし入れ墨が鍼治療の起源だとすれば世界各地に鍼治療の痕跡があるということになります。
だとすれば他の地域では何故鍼治療の文化が発展しなかったのか?考えてみると面白いですね。
一寸法師は鍼灸師!?(2009年8月)
北海道新聞に歌手の合田道人さんの連載で『あの日の歌景色』というのがあります。
童謡に関するエピソード満載で、たとえば『赤い靴』の女の子は実在したとか『アルプス一万尺』はアメリカ民謡となっているけどあれはアルプスの少女ハイジのアルプスではなくて日本アルプスのアルプスで「小槍(こやり)」という名の山が本当にあり、その高さが3030メートルでちょうど一万尺であるとか面白い内容の記事が書かれています。
2009年7月14日(火)の連載は『一寸法師』でした。
法師というのは一般的にはお坊さんを指しますが、髪をそった男の子や当時坊さんの格好をした鍼灸師も法師と呼ばれていました。
また、一寸法師は針を持っているところから、一寸法師は実は病気という鬼をやっつける鍼灸師だったのではないか、とあくまで推論ですがそう述べられていました。
(ちなみに鍼灸師が使う鍼の長さはいろいろですが、一般的に多く使われるのは一寸から一寸六分の長さの鍼でこれも合致しますね。)
私達鍼灸師からすればうれしい内容で、これまでも身近な一寸法師でしたがもっと親近感が湧きました。
鍼灸師のマスコットキャラクターにしたいぐらいです。
でもそうすると童謡の一寸法師、
「指に足りない一寸法師 小さい体に大きな望み~」
童謡の歌詞を変えなくてはならなくなりますね。(笑)
関連書籍
*合田道人さんの連載は本にもなっています。
『童謡の風景』(合田道人著、北海道新聞社)
『童謡の風景2』(合田道人著、北海道新聞社)
カンフーと功夫(2009年7月)
カンフーはジャッキー・チェンやブルース・リーに代表される香港映画によく出てくる中国武術をさしますが、本来は中国武術をさす言葉は「カンフー(功夫)」ではなく「国術」という言葉みたいです。
ちなみに「功夫」を辞典(現代中国語辞典 光生館)で調べてみたら、
- 本領、手腕、工夫
- 修練、努力
- 時間、ひま
と出てました。
ジャッキー・チェンやブルース・リーは武術の修練を積んだ人という意味で「功夫」が使われたのがおそらく中国武術そのものを指すようになったのでしょう。
中国では武術に限らず広く使用される言葉のようで、お茶でも功夫茶という使われ方をするようです。
功夫茶(または工夫茶と書く)は時間や手間を掛けお茶を楽しむ為のこだわり(工夫:手間ひま)だそうです。
日本の茶道はどちらかというと礼儀作法というか精神性を重視しているのに対し、中国の人々の功夫茶は香りや味というどちらかというと実用面を大切にしているところも面白いです。
もっと面白いのが功夫に「時間」という意味があることです。
映画やドラマのカンフーのマスターは必ずといっていいほど老人が出てきます。そして強いんです。
まぁ、ドラマだからっと言ってしまえばそれまでですが・・・。
でもここに「功夫」のというか中国文化・東洋文化のかけらが流れ出ているような気がするのですが。
一般的にスポーツの世界ではある年齢を越えるとスピードもパワーも衰えて弱くなると考えられています。
でも「功夫」は長い時間をかけて工夫し努力するという修練を積み重ねた「何か」なんだと思います。
そこには時間の積み重ねが必要で中国人・東洋人の時間の積み重ね・歴史の積み重ねに対する絶対的な信頼があるように思います。
そしてそのようにして生まれるたものが「技」であり「芸」なんだと思います。
鍼灸師も職人~勘・感覚を磨くことが大切~(2009年4月)
ユングはものを認識する仕方について感覚、思考、感情、直感の四つの方法があると言っています。
これらは単独で用いられるのではなく四つ全てが同時に認識するときに用いられますが人によりその割合に差が有り、そこからこの四つを性格分類に応用したりします。
私はユング心理学はよく知らないのですが認識方法が四つあるというこの考え方を面白いと思います。
私達は普段の日常生活や芸術などの場面で感覚、感情、直感が使われることはたくさんありますが、現代社会は科学技術に代表されるように思考という認識方法により重きがおかれているような気がします。
もちろん思考が悪いわけではなく有用な道具なのですから上手く用いるべきですが、他の認識方法ももっと活用したほうが良いと思います。
勘という言葉がありますが、昔の職人などはこの勘を磨いて優れた工芸品を作っていました。
この勘は直感というよりも感覚を磨いて作り上げるものだと思いますが現代でも東京大田区の町工場などで機械よりも細かく正確に研磨する職人さんがいるそうです。
鍼灸師も職人なのですから感覚を磨いて勘を作り上げなくてはいけません。鍼灸師たるもの、そのための勘・感覚を磨く道筋をきちんと考えるべきだと思います。
気について(2009年2月)
東洋医学・思想において気というのはとても重要な言葉です。
今回は気という言葉が英語でどういうふうに訳されたかを『気の思想』(東京大学出版)のなかの附論『西洋文献における「気」の訳語』から羅列してみます。
ちなみに英語の日本語訳は参考として付けてみました。
| breath | 息、呼吸、一息、瞬間、(風の)そよぎ、いぶき、しるし、生命 |
| air | 空気、大気、空中、空、そよ風 |
| vapour | 蒸気、水蒸気 |
| stream | 流れ、小川、(人・ものの)流れ、傾向、風 |
| vital fluid | 流体、体液、流動物、流動性の |
| temperature | 温度、体温、(感情の)強さ、高熱 |
| energy | 精力、活気、勢い、元気、(活動)力 |
| anger | 怒り、立腹(させる) |
| ether | エーテル、(古い物理学で光,熱などの媒体とされた仮説上の物質)、精気、天空 |
| force | 力、勢い、風力、腕力、暴力、圧力、武力、軍隊、総勢、集団、気力、たくましさ、支配[影響]力、勢力、説得力、効力、(ことばの)真意 |
| material force (material) | 物質の、物質的な、肉体的な、世俗[物欲]的 |
| vital force (vital) | 生命の[に関する]、生命の維持に必要な、不可欠な、致命的な、活気に満ちた、生き生きした |
| the prime force (prime) | 首位の、主な、最重要な、根本的な、最上の、優秀な、最良の、最初の、原始的な、素数の |
| circulatory system of the body | 肉体がもつ循環体系 |
いろんな訳がありますね。
当然ながら気という言葉そのものは英語にはありません。
私達が気という言葉を使うときも文脈によっていろんな意味を持ちますし、日本と中国でも日本では情緒的な使われ方、中国では動的なエネルギーとして具体的な実質を中に含んだ使われ方とちょっと異なるところがあります。
哲学としての気の概念も時代によって多少の変化があります。
このようなことがいろんな訳を生じた理由でしょう。
当たり前かもしれませんが英語のそれぞれの訳は気という言葉の持つ何かをちゃんと表しています。
私達が普段何気なく使っている気という言葉は解かって使っているのですが実はあやふやなところがあり、そのあやふやなところを知るきっかけとしてこのような英語訳は大変参考になります。
参考文献
『EXCEED英和辞典』三省堂
『気の思想―中国における自然観と人間観の展開』東京大学出版会
太陽人 イ・ジェマ ~韓国医学の父~(2008年9月)
以前に『宮廷女官チャングムの誓い』や『ホジュン』を紹介しましたが今回は『太陽人 イ・ジェマ ~韓国医学の父~』を紹介します。
イ・ジェマも実在の人物で韓国独自の四象医学というものを確立した人です。
四象医学とは、人間の体質を「太陽人」「少陽人」「太陰人」「少陰人」の4つに分類し、疾病によって治療するのではなく、それぞれの体質に合わせて治療する漢方医学です。
それまでの韓国の医学は中国の漢方医学理論を使っていましたがこの四象医学によって初めて韓国独自の医学理論体系が出来ました。
ちなみに四象とは易から来ていて、陰陽がさらに分かれて太陽・少陽・太陰・少陰の四象になり、四象がさらに分かれて当たるも八卦当たらぬも八卦の八卦になります。
ドラマはイ・ジェマの幼少から四象医学を創るまでで演出はコ・ヨンタクさんです。
ホ・ジュンやチャングムのときの演出はイ・ビョンフンさんで演出の違いを楽しむのもひとつです。
DVDが出ていますので興味のある方は見てみては如何でしょうか?
散歩・逍遥と呼吸法、鍼治療で気の活性化を(2008年8月)
今回は散歩・逍遥について。
国語辞典(旺文社 松村・山口・和田編)で散歩・逍遥を調べると、
散歩:気のむくままにぶらぶら歩くこと。そぞろ歩き。
逍遥:気ままにぶらぶら歩くこと。そぞろ歩き。
散歩・逍遥どちらも、こころのままにぶらぶら歩くことです。
当院でも患者さんに養生として散歩をよく勧めていますが、東洋医学的には以下の効能があります。
- 気血をよくめぐらせる。
- 上にあがった気を下に引き下げる。
- 足腰(腎の臓)を鍛える。
※東洋医学では足腰は腎の臓と関係の深い場所の為。 - 心身をほぐすリラックスの働き。
散歩と同じ様に歩くことによる健康法としてウォーキングがあります。
ウォーキングは、健康づくりを目的とした歩行運動(walking exercise)のことで、ジョギングやランニングと比較して運動強度が低いことから、日常生活の中で、いつでも、どこでも、気軽に実施でき、しかも病弱者や低体力者、高齢者でも体力に応じて安全に行えるのが特徴である。
健康づくりのウォーキングは、毎分100m程度の早足歩きを1日30分以上、毎日続けることが必要となる。
(現代用語の基礎知識2006より)
ウォーキングと散歩の大きな違いは散歩にはゆっくりぶらぶらあるくことにより心身をほぐすリラックス作用があるということです。
運動量としてはもちろんウォーキングのほうが高いので目的に応じて使い分けるといいと思います。
散歩の効能にあげた「上にあがった気を下に引き下げる」というのはとても大事なことです。
というのも、のぼせ・めまい・悪心などの症状が出る中医学における気逆という状態までいかなくても上に気が集まりすぎて下が虚ろになる状態になりやすいのです。
このような状態を上実下虚といいます。
反対の上虚下実という状態が健康な状態です。
お腹でいうと上虚下実は鳩尾のあたりが適度に柔らかくお臍の下の丹田あたりが充実した状態です。
逆に上実下虚では鳩尾のあたりが緊張して堅くなりお臍の下の丹田あたりがぶよぶよになります。
上虚下実の状態を作るのに幾つかの方法がありますが、その一つが静坐法(呼吸法)です。
面白いのが藤田式息心調和法(息心調和道)という呼吸法のなかに鳩尾が緊張して堅くならない為に鳩尾に手を当てて呼吸をする方法があります。
鍼では例えば無分流打診術などでは鳩尾のあたりの腹部の緊張を邪として捉え直接鍼をし丹田には火びきの鍼というもので丹田が充実するようにします。
上虚下実の状態を作るには呼吸法や鍼がよいのでしょうが軽いものであれば散歩・逍遥でまかなえます。
それにしても大局的な立場に立つと、散歩・逍遥も呼吸法も鍼も同じ道の中にあるのですね。
鍼と針(2008年6月)
「はり治療」の「はり」という字には鍼と針とがあります。
大漢和辞典(藤堂明保編 学習研究社)によると
針
1.皮や布地などを縫うためのとがった道具。ぬいばり。
2.漢方治療の一つ。
3.はりのように細長くて先のとがっているもの。
鍼
漢方医術で治療に用いるはり。転じて縫いばり。
このように鍼も針も両方「縫いばり」、「治療用のはり」の意味があり全く同じ意味つまり異体字(同じ言葉に異なった漢字があるもの)です。 ただ日本では慣習的に「縫いばり」には「針」の字が、「治療のはり」には「鍼」の字が多く使われています。
「はり治療」で「はり」を刺すと、患者さんによるのですが敏感な方だと重だるくなったり、温かくなったり、ときには何かが流れるような感じがする事があります。
これはよい反応なのですが、「鍼」という字はもともと金と咸(感じる)からできた会意文字なので、もしかしたら、治療の為「はり」を刺すと何か身体に感じるというところから「鍼」の字を治療のはりに使うようになったのかもしれません。
そうだとすると「はり」という字ひとつにもに込められた思いがあるようで面白いですね。
桃太郎は金太郎?~昔話と東洋思想・五行説との関係~(2008年5月)
現代においては大分薄れてはいますが、東洋的なものの見方考え方というのが昔から私達に大きな影響を与えてきました。もちろんその中には意味の有るものもあれば意味の無い迷信のようなものもありますが・・・。
日本に伝わる桃太郎のような昔話のなかにも五行説などの東洋思想の影響が深く関わっているとされています。
五行説というのはすべてのものは木・火・土・金・水の五気により成り立っているというものです。
桃太郎が生まれた桃は五行説では金、お供の申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)は方位でいえば西の方角でこれも五行説で金なのです。
桃太郎って金太郎?って思うぐらい金と繋がっていますね。
一方、鬼は方位でいえば鬼門(丑・寅)つまり北東の方角です。
日本の鬼はウシにような角をもち、虎柄のパンツを穿いていますが、この鬼門・丑(ウシ)寅(トラ)からきています。
鬼門である北東の方角は五行で土であり、五行の相生関係により土から金が生まれるため、金(桃太郎)が強くなると土(鬼)が弱くなるというふうに五行で説明する考え方があります。
まぁ、ここまでくると少しこじつけの様な気もします。
北東は八卦の艮で考えると土ですが干支の丑寅で考えると丑は土ですが寅は木になります。
まぁ五行が木でも五行の相克関係により金(桃太郎)が木(鬼)を切り倒すので変わりませんが・・・。
こじつけのようなところも有りますが、桃太郎を東洋思想でこんなふうに考えるのも楽しいものです。
東洋医学・鍼灸医学を学ぶ効用~新年のご挨拶にかえて~(2008年1月)
新年明けましておめでとうございます。
私も鍼灸師になって今年で10年という節目の年になりました。まだまだ至らぬところが多々あると思いますが日々努力して少しでも皆様方のお役に立てるよう頑張りたいと思っています。
最近、東洋医学・鍼灸医学を学んで本当に良かったと特に思うようになりました。
東洋医学・鍼灸医学を学ぶ効用は3つあると思います。
1つ目は、健康に役立つということ。
2つ目は、東洋医学・鍼灸医学は伝統文化なのでそれを学ぶことは日本の文化・東洋の文化を学ぶことになるということ。
3つ目は、東洋医学・鍼灸医学はその根底に易や老荘思想などの東洋思想・東洋哲学の深い哲理によって打ち建てられています。
この哲学を学ぶことは、混迷する現代を生きていく為の大きな助けに必ずなると思います。
肩肘を張らない、こころも身体も軽くなる生き方、それは健康になる生き方だとも思います。
皆様にとって、今年も良い年になりますように!
本年も宜しくお願い致します。
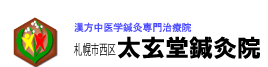
 鍼灸・漢方・東洋医学・東洋思想・気功編メニューへ戻る
鍼灸・漢方・東洋医学・東洋思想・気功編メニューへ戻る