「院長の独り言」ジャンル別
「院長の独り言」ジャンル別~鍼灸・漢方・東洋医学・東洋思想・気功編~
鍼灸・漢方・東洋医学・東洋思想・気功編 ―2023年-2025年―
- フロンティアで会いましょう~最新科学が解き明かす東洋医学のパワー(2025年10月)
- “新”東洋医学(2025年8月)
- 腹診と日本文化(2025年7月)
- ツボ(2025年6月)
- 扁鵲(2025年5月)
- 四診~望聞問切~(2025年3月)
- 難経腹診の五臓の配当について(2025年2月)
- オ血に使用するツボ(2024年12月)
- 糖尿病(2024年11月)
- 高血圧(2024年10月)
- 不眠(2024年8月)
- 便秘(2024年7月)
- 周易私論 2(2024年6月)
- 東洋医学に関するテレビ番組が放送されました(2024年5月)
- 周易私論(2024年4月)
- 皮膚刺激と筋肉刺激(2023年12月)
- 折衷主義(2023年11月)
- 老荘思想(2023年9月)
- 周易と老子(2023年8月)
- 周易と老子(2023年8月)
- 温故知新(2023年7月)
- 鍼の響き(2023年6月)
- 易の話のつづき(2023年5月)
- 山沢損と風雷益(2023年4月)
フロンティアで会いましょう~最新科学が解き明かす東洋医学のパワー(2025年10月)
「フロンティアで会いましょう~最新科学が解き明かす東洋医学のパワー」は10月6日(日)23時からNHK総合で放送されました。
鍼灸や漢方薬の有効性を示す様々なトピックスが紹介されていました。
幾つか列挙すると、
①大建中湯が腸内環境を改善する
②茵蔯蒿湯が黄疸に有効である
③アルテミシア アヌアが癌に有効な可能性がある
④敗血症に足三里の鍼が有効な可能性がある(ラットの実験から)
⑤イギリスでうつ病の治療に鍼が有効であると示された
⑥バトルフィールド アキュパンクチャー(アメリカ軍の耳鍼)が被災地などで活用されている
⑦アフリカで結核やエイズの患者にお灸が活用されている
東洋医学や鍼灸の有用性が紹介されるのは嬉しいことです。
“新”東洋医学(2025年8月)
『“新”東洋医学』は2025年8月4日から毎週月曜日午後9:30〜午後10:00にNHK・Eテレで放送されています。
東京女子医科大学附属東洋医学研究所所長の木村 容子先生、料理研究家、国際中医薬膳師のワタナベマキ先生、鍼灸師、中国政府認可世界中医薬学会連合会認定国際中医専門員の石垣 英俊先生が出演されています。
一般の視聴者向けに手軽にできる薬膳、ツボ押しなどが紹介されています。
東洋医学が紹介されるのは嬉しいことです。
腹診と日本文化(2025年7月)
腹診は中国や韓国ではあまり発達せず、日本において大きく発達しました。
中国や韓国では、身分の高い人の体にむやみに触れてはいけないという儒教の教えがあるからとされています。
日本にも儒教は伝わっていますが、日本において腹診が大きく発達したのは、腹診の有用性と日本文化の特殊性も関係しているように思います。
ハンティントンの『文明の衝突』では、世界の文明を、西欧文明、東方正教会文明、イスラム文明、仏教文明、ヒンドゥー文明、アフリカ文明、ラテンアメリカ文明、中華文明、日本文明に分けており、日本は一国のみで成立する孤立文明とされています。
考えてみると日本は、鍼灸もそうですが、漢字をはじめとして多くのものを中国から学びましたが、そこには取捨選択や日本風のアレンジがあるように思います。
例えば宦官という制度が中国や韓国ではありましたが、日本にはありませんでした、その代わり大奥という制度がありました。
腹にたいしても日本は独特な見方をしているように思います。
例えばことわざで、「腹が立つ」は怒りの感情を、「腹を決める」は心を決めることを、「腹を割る」は、隠さずに本心を話すことを意味します。
つまりココロの働きを腹という場所に置いていたということになります。
中国では心は心の臓であり、ココロの働きでもあります。
英語でもHeartは心臓でもあり、ココロでもあります。
つまり英語でも中国語でもココロの働きの場所は胸になります。
(もちろん科学の発達とともにココロの働きの場は頭に変わりますが・・・)
近年脳腸相関が注目されています。
脳と腸が自律神経やホルモンなどによって、密接に影関係しているというものです。
もしからしたら昔の日本人はそのことに気づいてたのかもしれません。
ツボ(2025年6月)
今回はツボについて
ツボが何なのかというのは、けっこう難しい問題なのですが、一応「ツボは病の反応が出る場所であり、診断点であり、治療点である」と一般的に定義されています。
歴史的な大まかな流れをみてみると
『医心方』(丹波康頼著 平安時代)
〇肺兪二穴:第三椎の下の両旁、各一寸半に在り。刺入るること三分。留むること七呼。灸は三壮。足の太陽、膀胱。
肺、寒熱にて呼吸得ず。臥すればしわぶきし、上気し、沫を嘔き、喘気、胸満し、脊急り、食を嗜まず、背強ばり目反り、盲見し、瘛瘲にして、泣出で、死して人知らざる、を主る。
『鍼灸大成』(楊継州著 中国、明の時代)
〇痰喘咳嗽門
咳嗽:列缺、経渠、尺沢、魚際、小沢、前谷、三里、解谿、崑崙、肺兪、膻中
『療治之大概集』(杉山和一著 江戸時代)
〇咳嗽:天突、肺兪、下脘、上脘、不容、章門、百会
以上のように、〇〇の病には〇〇のツボというように主治穴として発展した流れが一つあります。
次に要穴という考えがあります。
要穴は五行穴、五兪穴、絡穴、郄穴、募穴、背部兪穴、八会穴、四総穴などがあります。
ここでは五行穴、五兪穴を説明します。
五行穴は木穴、火穴、土穴、金穴、水穴です。
五兪穴は井穴(心下満を主る)縈穴(心熱を主る)兪穴(体重節痛を主る)経穴(喘咳寒熱)合穴(逆気而泄)となります。
例えば咳であれば五兪穴の経穴であるとか、五行穴の金穴(肺は金なので)を使うのも一つの方法です。
また、難経の69難の「虚すればその母を補え」で太淵、太白などの土穴を使うのも一つの方法です。
このように要穴というのはある程度理論化されたものと考えることが出来ます。
次に穴性という考え方があります。
これは中医学の考え方になりますが、ツボにどういう働きがあるかを当てはめたものです。
例えば足三里や中脘などには補気作用のあるとするものです。
なので、例えば気虚によって何らかの症状が起こっている場合、気を補う治療を行います。
漢方薬では六君子湯や補中益気湯などが補気の働きがあります。
鍼灸では足三里や中脘など補気の働きのあるツボを使うこととなります。
中医学の考え方では理論的にかなりスッキリしたものになっています。
その他では西洋医学、特に解剖学の知見からツボを理解しよという考えもあります。
最近ではファシア、筋膜が注目されています。
また、電気抵抗の違いに注目したツボの考えかたもあります。
今後もいろいろなツボの捉え方、解釈が出てくると思います。
それは楽しみでもあります。
扁鵲(2025年5月)
中国の伝説の名医は、岐伯、扁鵲、華佗など色々いますが、今回は扁鵲について。
扁鵲は耆婆扁鵲という言葉があるようにインドの耆婆と並び称されています。
古い石刻では鳥の姿をしています。
中国の戦国時代の鄭の人、姓は秦、名は越人、名医として知られ扁鵲と呼ばれたとされています。
『史記』に伝説的な話が載っています。
〇長桑君という仙人にもらった薬を飲んで人の体の中を透視できるようになった。
〇虢の太子が死んだのを蘇らせた。
〇斉の桓候に病だからと幾度も治療を勧めるも桓候は自分が病気だと思わず断り、扁鵲が去った後に亡くなった。
扁鵲は遍歴医だったようで黄河流域に広範囲に扁鵲を祭った薬王廟があります。
何故扁鵲という呼称になったのかは分かりませんが、鵲はカササギで、めでたい知らせを告げる鳥とされています。
また、人面鳥身の神像の石刻に山鵲の文字が刻まれているのがあり、山鵲はカササギに似た鳥だそうです。
山鵲は別名鷽といい未来を知る鳥だそうです。
いづれにしても扁鵲にふさわしいように思います。
四診~望聞問切~(2025年3月)
東洋医学の診察法を四診といいます。
四診は望診、聞診、問診、切診の四つをいいます。
簡単に説明すると、
望診は西洋医学の視診に相当するもので、患者さんの舌や顔面、体全体の状態を目で観察するものです。
聞診は聴覚と嗅覚によるもので、患者さんの呼吸音、話し方、セキの音、体臭、口臭などを観察します。
問診は様々な身体の状態を質問して患者さんの情報を集めるものです。
切診は触覚によるもので、脈診や腹診、背中や手足のツボなどを観察します。
望、聞、問、切の四つを漢和辞典で漢字を調べると、
聞は、「扉を閉じて中がよく分からない、へだたりを通して耳に入る」というものです。イメージ的には壁に耳を当てて中の音を集中して聞いている感じでしょうか。
問は、「扉を閉じて中がよく分からない、口で探り出す」というものです。イメージ的には例えば、閉じた扉の向こうで大きな音がして、「今音したけどどうしたの?」などと色々質問して中の様子を知ろうとする感じでしょうか。
切は、「刃物をピタッと切り口に当てる」というもので、脈診なりツボを診るときに指を皮膚にピタッと当てるところからこの漢字が使われたと思います。
それぞれその漢字が使われた理由が直ぐに分かる気がするのですが、問題は望という漢字です。
「みる」という意味の漢字は、見る、診る、観る、視るなど沢山あります。
その中でなぜ望という字が使われるのか?
望は、「人が伸びあがって遠くの月をまちのぞむ」です。
つまり望は基本的に遠くを見るときに使われる漢字です。
話は少し脱線しますが、私はあまり美術館には行かないのですが、それでもたまに行くと、美術に詳しそうな人が絵画を観るのに近づいて観たり、少し離れて観たりを繰り返しているのを見かけたりします。
昔の人が望という字を使ったのはこういうことなのではないか、と思います。
「木を見て森を見ず」ということわざがありますが、全体を見ることの大事さ、もちろん「森を見て木を見ず」になってはいけませんが、細部(部分)と全体、両方診ることの大事さを望という漢字が教えてくれているように思います。
難経腹診の五臓の配当について(2025年2月)
腹診は中国や韓国ではあまり発達せず、日本において大きく発達しました。
腹診には漢方薬的な診方、『難経』的な診方、募穴(腹部にある五臓六腑を代表するツボ)による診方、夢分流という独特な診方などいろいろな診方があります。
今回は難経腹診の五臓の配当について、ちょっと脱線した話をします。
難経腹診の五臓の配当は、心下(心窩部)で心の臓を診る、大腹(胃カン部)で脾の臓を診る、右脇下で肺の臓を診る、左脇下で肝の臓を診る、小腹(臍下)で腎の臓を診ます。
これは鍼灸学校で、当たり前に暗記させられるものですが、私はこれに疑問を抱いていました。
現在は扁鵲の正解と一致するかどうか分かりませんが、自分なりの答えを持っています。
その当時の疑問はこうです、『難経』の一つの大きなテーマはマクロコスモスとミクロコスモスが相関しているということです。
自然と人間が相関している、中医学用語では天人相関といいます。
なので、『難経』では季節によって脈が変化するというようなことも書かれているわけです。
マクロコスモス(自然)とミクロコスモス(人間)の関係を『難経』では陰陽五行で説明しています。
心は火で南、脾は土で中央、腎は水で北、肺は金で西、肝は木で東です。
これをお腹に方位として当てはめると、心下が南、大腹が中央、小腹が北、右脇下が西、左脇下が東となります。
これは実際の方位と比較すると鏡像になっている、つまり上下は一致するけれども、左右は反対になっています。
実際の方位とお腹の方位が一致しないのは間違っていると考えていました。
私なりの答えを述べてしまうと、犬も馬も動物は四つ足です。
人間は直立していますが、動物でもあるので四つ足、うつ伏せが正常な姿勢と考えるとお腹の方位と実際の方位が一致します。
当たり前として暗記しているような知識もその背後にある理論的な背景などを改めて考えてみるのも大事なことだと思います。
オ血に使用するツボ(2024年12月)
今回はオ血に対して使用するツボを幾つか簡単に説明します。
まず、三陰交、このツボは昔は女三里とも呼ばれ、血の道症(月経前症候群や更年期障害などの婦人科疾患)によく使われました。
血虚のときは補血としても使えます。
血に対するツボとしてはある意味オールマイティに使われるツボです。
次に血海、このツボは名前に血という字が付いているように血と深い関係があるツボです。
このツボも血を補うのにも使えます。
膈兪、このツボは八会穴のなかの血会となっており、このツボも血と関係が深く、補法にも瀉法にも使えます。
藤本先生は血に関係が深いツボとして、膈兪、血海、三陰交、公孫を重視されています。
あと、オ血に使用するツボとして臨泣を重視されています。
中医学のテキストでは、テキストによって多少異なりますが、心兪、次リョウ、百会などもオ血に対して有効なツボとされています。
参考文献
『経穴解説』(藤本連風著、メディカルユーコン)
『常用兪穴臨床発揮』(李世珍著、人民衛生出版社)
糖尿病(2024年11月)
今回は糖尿病について。
糖尿病は東洋医学では消渴病といいます。
消渴病は多飲、多食、多尿の三多の症状と、他にるい瘦、尿が甘いなどの症状があります。
『実用中医内科学』(上海科学技術出版社)では、
・肺胃燥熱
・腸燥津傷
・肝腎陰虚
・陰陽両虧
・脾胃気虚
・湿熱中阻
以上のように分けています。
実は東洋医学の理論的な分析はテキストにより多少異なります。
『中医内科』(金剛出版)では、
上消(肺が中心):多飲、口渇
中消(胃が中心):多飲、多食、るい瘦
下消(腎が中心):多尿、頻尿
と分けています。
いづれにせよ、熱邪、燥邪がカギとなるように思います。
高血圧(2024年10月)
今回は高血圧について、簡単に述べます。
高血圧は血圧計による測定で140/90mmHg(自宅での測定の場合は135/85mmHg)以上の状態と定義されています。
年齢にかかわらずこの数値が基準となりますが、一般的に年齢を経ると血圧は上がりますので、20代と60代が同じ基準というのは厳しすぎるのではないか、上の血圧(収縮期血圧)は年齢+90ぐらいを基準にしてもいいのではないかという意見もあるようです。
東洋医学では高血圧をどう考えるかということですが、残念ながら東洋医学では高血圧という概念がありません。
東洋医学は機械を使わず五感を大事にしています、そのメリット、デメリット両方あると思いますが、ここではそれは置いておいて、では東洋医学では高血圧をどう考えるのか?
一つの考え方として、症状から論理的に考えるアプローチがあります。
高血圧のよくみられる症状として、頭痛やめまいがあります。
頭痛もめまいも東洋医学的に分析されています。
頭痛:風寒、風熱、風湿、肝陽、気虚、血虚、腎虚、痰濁、オ血など
めまい:肝陽上亢、気血虧虚、腎精不足、痰濁内蘊、オ血阻絡など
以上から肝火、痰熱、腎虚などが深く関係しているといえると思います。
よって高血圧は主に肝鬱化火タイプ、痰湿中阻タイプ、陰虚陽亢タイプと分けることが出来ると思われます。
もう一つは脈やツボの状態などから導き出すアプローチがあります。
具体的に説明するのは難しいのですが、経験的に高血圧の方は肝、腎、気逆、熱邪、痰湿が関係することが多いと思います。
どちらのアプローチからでも、だいたい同じ結論にたどり着きます。
不眠(2024年8月)
今回は不眠について、東洋医学的な説明を簡単にではありますがしてみます。
不眠の原因としては、ストレスなどによる情志の失調、心労が続いたり出血などによる血虚、陰虚、邪熱、心気虚、飲食の不摂生などによる胃の不調和など様々あり、東洋医学では、以下のように分類しています。
心脾両虚:過度の心労、産後の失血、手術後の衰弱、高齢などによる気血不足により心神を養えずに不眠が起こる
陰虚火旺:心陰が不足することにより熱邪が生じ不眠が起こる
心腎不交:腎陰が損傷し心陰を助けれずに不眠が起こる
肝鬱血虚:ストレスなどによる情志の失調により肝が傷つき不眠が起こる
心虚胆怯:もともと心気が虚していて驚きやすく怖がりで心神が不安定のため不眠が起こる
痰熱内擾:痰熱が体の中に生じ心神を擾乱するために不眠が起こる
胃気不和:飲食の不摂生などによる胃気の不和により不眠が起こる
参考文献
『実用中医内科学』(上海科学技術出版社)
便秘(2024年7月)
今回は便秘について、東洋医学的な説明を簡単にではありますがしてみます。
まず便秘の原因として、熱邪によるもの、気の停滞によるもの、気や血や陰液の不足によるもの、寒邪によるものなどが考えられます。
それで、以下のように便秘のタイプを東洋医学(中医学)では分けています。
熱秘:熱邪が胃腸にこもることにより生じる便秘、そのため津液が損傷し大腸が乾燥する。
ツボとしては、合谷、曲池の鍼など。
気秘:ストレスや運動不足などにより気が停滞することにより生じる便秘。
ツボとしては、中カン、行間の鍼など。
虚秘:気虚便秘、血虚便秘、陰虚便秘の3種類に分かれるが、いづれにしても大腸の働きが低下することにより便秘が生じる。
ツボとしては、脾兪、胃兪の鍼など。
冷秘:身体を冷やす飲食物の摂りすぎや陽気の不足により寒邪が生じることにより起こる便秘。
ツボとしては、神闕、気海の灸など。
また、どのタイプの便秘に対しても大腸兪、天枢、支溝などのツボへの鍼も有効だと思います。
その他に便秘で著名なツボとしては、沢田流神門の灸、柳谷便秘穴など様々あります。
参考文献
『実用中医内科学』(上海科学技術出版社)
周易私論 2(2024年6月)
今回は火山旅について述べたいと思います。
外卦が火、内卦が山の卦が、何故「旅」と名付けられたのか。
火のコアイメージは、誰もが求める華やかな答え、ゴール。
山のコアイメージは、静かに止まっている。
外卦火、内卦山の卦のイメージは、遠くのゴールを目の前に止まっている、というもの。
おそらく商人か何かが、夜になり、野宿か或いは宿に泊まって、遠くの街の灯りを見ている、というイメージではないでしょうか。
なので、旅という卦には、レジャーの旅行のような楽しさというよりは、少し寂しさを伴っているようにも感じます。
卦辞は、旅小亨旅貞吉。と書かれています。
ゴールを前に一時的に止まっているので、少しくとおる。ゴール、答えが分かっているのでそれに向かって貞であれば吉。ということでしょう。
(爻辞の説明は今回は割愛します)
火山旅は、水山蹇の困難を前に足がすくんで動けない、とは異なります、目の前にあるのは困難ではなくゴール・お宝なので、同じく静かに止まっていてもニュアンスが異なります。
このように易の卦の名前や卦辞などから易を考察するのも楽しいですし、もっとシンプルに吉凶を占うのも易の楽しみの一つです。
吉凶も考えてみると難しく、例えば朝、仕事に行くときに雨が降ったとすると、濡れて風邪を引くかもしれないし、傘を持つ手間が増えるので凶とも言えますが、もし自分が農家で日照りが続いた後の雨なら恵の雨で吉とも言えます。
同じ事象でも立場によって、吉凶が変わることもあるでしょう。
周易は首卦が乾で、陽を尊いとし陰を卑しいとし、その体系は儒教の影響が大きいといえます。
実際、周易は儒教の経典、四書五経の筆頭です。
現在は失われてしまいましたが、帰蔵易は首卦が坤、連山易は首卦が艮であり、現在の周易とはだいぶ異なっていたと思われます。
老荘思想は堅強よりも柔弱であることを良しとしているので、もしかすると帰蔵易は老荘思想と似ていたかもしれません。
いづれにせよ、古代に思いを馳せ、古典と遊ぶのも楽しいものです。
関連記事
「周易私論」(2024年4月)
東洋医学に関するテレビ番組が放送されました(2024年5月)
今月、東洋医学に関する番組がNHKテレビで放送されました。
最新の科学的研究から東洋医学の治療効果のメカニズムの一端が解明され、大変興味深く拝見しました。
一つは、2024年5月16日(木)に放送された『あしたが変わるトリセツショー』。
ツボとは「不調に応じて体の表面に炎症が起きる場所」だというもの。
ツボの治療効果は、鍼を刺すことにより、脳血流が増加し、脳内で鎮痛物質「オピオイド」が分泌され、痛みをやわらげる効果。
凝り固まっていた筋膜のシワが伸び、筋肉を柔らかくし筋肉にたまった痛み物質を押し流し、凝りが軽減する効果。
の2つが考えられるというものでした。
もう一つは、2024年5月19日(日)放送の『NHKスペシャル「東洋医学を“科学”する~鍼灸(しんきゅう)・漢方薬の新たな世界~」』
漢方薬の治療効果には腸内細菌が大きく関わっているというもの。
鍼灸の治療効果には迷走神経などの自律神経を介して免疫などの作用に大きく働きかけているというもの。
鍼灸のそのような治療機序を応用して耳に電気刺激を与えて病気の予防に役立てようという研究がされているというもの。
等々様々な事例が紹介されていました。
どのような形であれ、東洋医学の良さを伝えてくれるこのような番組は、東洋医学の一端を担う我々鍼灸師にとっても、嬉しい限りです。
周易私論(2024年4月)
易は人類の宝です、宇宙の様々な現象を64の物語り(構造パターン)として理解しようとするものだと思います。
活用しないのはもったいない、しかし、難解なために、なかなか内容を理解できません。
今回は、コアイメージで易を理解しようという私論であり、試論の紹介です。
易をコアイメージで理解するというのは、実は昔から有ります。
乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤の八卦に天、沢、火、雷、風、水、山、地という自然界の8つの現象が当てはめられています。
これが昔からあるコアイメージです、しかし現代では分かりづらいので、現代に合った分かりやすいコアイメージを提供しようというものです。
例えば、水雷屯という卦があります。
私の考える水(坎)のコアイメージは、解決しなければならない問題・困難・天敵となります。
私の考える雷(震)のコアイメージは、賑やかに動く、表に現れて動くとなります。
なので、コアイメージで水雷屯を考えると、目の前の問題・困難を解決しようと活発に動いている状態と考えられます。
屯の字そのものも、地中の種から芽が出て、地面から出ようとして出きらない、行き悩むという意味です。
まさに壁にぶつかって解決しようとしてもがいてる、困難な状態ということで、占いの方では4大難卦の一つとされています。
卦辞(卦に書かれている言葉)には、屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建候。と書かれていますが、4大難卦なのに元亨利貞(おおいにとおる、ていによろし)とはどういうことか。
私の解釈はこうです、交通事故も自分が正しくても周りが悪くて起こる場合もあるし、周りには問題が無くて自分が悪くて起こる場合もあるように、元亨(おおいにとおる)は始めから道には障害物が無く通っている、つまり自分がこじらせている。利貞(ていによろし)は自分がこじられているのだから本来の天意に沿っていれば滞りなく進む、勿用有攸往(ゆくところあるにもちいるなかれ)は自分で行動するな、利建候(こうをたてるによろし)は誰か適任な他の人に任せよ、ということだと思います。
あと、卦には6つの爻が有り、それぞれに言葉が書かれています(爻辞)。
この爻をどのように解釈するのかも難しいのですが、私は物語の6つの展開の可能性として考えています。
ベタな例ですが、田舎からロックスターを目指して上京した若者が一生懸命音楽活動をしているが売れない、という物語があったとして、これは屯の物語としても捉えることができると思います。
ここでは違いが分かりやすい4爻と上爻で説明します。
屯の4爻の爻辞には、乗馬班如。求婚媾往吉。无不利。と書かれています。
私の解釈はこうです、馬に乗って急ぐように活動を頑張っているがなかなか進まない。敵だと思っていた困難から仲良くしたい(結婚)を申し込まれる。そのまま行動すれば吉。スパッといかないことはない。と、すぐにでも売れるような最高の展開もあれば。
屯の上爻の爻辞には、乗馬班如。泣血漣如。と書かれています。
私の解釈はこうです、馬に乗って急ぐように活動を頑張っているがなかなか進まない。血の涙が連なって流れている。という、最悪な状況の展開もあります。
物語に一回変換することで、目の前の現実の事象を客観視することが出来るのも易の効用の一つではないかと思います。
いづれにせよ、易の理解への一助になれば幸いです。
皮膚刺激と筋肉刺激(2023年12月)
鍼の治療は大きく分けて、皮膚刺激と筋肉刺激に分かれると思います。
分かりやすく説明すると、鍼による皮膚刺激とは、鍼による皮膚への刺激が自律神経を介して内臓や免疫などの働きを改善するというものです。
鍼による筋肉刺激とは、筋肉の強張りに鍼をすることによって筋肉の動きや血流を改善するというものです。
症状によってこの二つを上手く使い分けれれば、より早く症状の改善が見込まれると思います。
私は古典を研究しているわけではないので、深く古典を研究されている先生方に叱られるかもしれませんが、『難経』の七十一の難に書かれている、衛気と栄気(営血)の刺し方の使い分けは、皮膚刺激と筋肉刺激のことを言っているのではないかと個人的に思っています。
そうであれば、全く土台の異なる東洋医学と西洋医学が少しつながって面白いです。
また、『難経』の二十二の難の是動病と所生病の違い、気と血、経脈と臓腑、外邪と内傷などいろいろな説がありますが、別の視点があるかもしれません。
そんなふうに古典を読んでみるのも面白いと思います。
折衷主義(2023年11月)
折衷主義とは、クライアントの問題に応じて最も適した方法をとる立場で、既存の各理論から活用できるものは何でも使う立場のことです。
私も患者さんの症状によっては他の理論も使うので実際は折衷主義の立場をとっているのですが、折衷主義に対する反論もあります。
一つの理論を学ぶのにも5年10年とかかるのに、たくさんの理論をマスターできるのか?
折衷主義とは器用貧乏ではないか、何でも浅く知って深くないので効果を上げれないのではないか?
それに対する反論として
理論をマスターすることの意味として各理論のすべてを知っている必要はなく目の前のクライアントに必要な分を知っていればよい。
また各理論にはそれぞれ得意分野とあまり得意でない分野がある。
ということがあると思います。
ただ、理論自体は大切なもので、現在の患者さんの状態に対して説明、解釈し、未来の予測を立て、治療の手段を決めるものです。
また臨床家タイプや研究者タイプなど立場によっても理論にたいする姿勢が違ってくると思います。
卑近な例ですが、町医者と大学病院で研究している医者のように、研究者は理論をきちんと構築することが仕事で、良い理論が構築できればそれがゆくゆくは全体の治療の質を上げることにつながります。
町医者は目の前の患者さんの為に最も有効そうな手段を選択していくのだと思います。
いづれにしても理論は大事なものだと思います。
老荘思想(2023年9月)
『老子』とその後の時代の『荘子』、その二つの思想を合わせて老荘思想といいます。
東洋思想の中でも私の好きなものの一つなのですが、実は日本文化に大きな影響を与えているのです。
老荘思想の日本への伝わりは一つは漢学(中国学)として。
特に江戸時代は官学として儒教が取り入れられました。
なので漢学の中心は儒教ですが、儒教以外も伝わっておりその中の一つとして老荘思想も伝わっています。
もう一つの流れは仏教を通して。
仏教はインドで釈迦によて生まれた宗教ですが、龍樹によって空を説いた大乗仏教が生まれ、その他にも唯識派や土俗の宗教を取り込んだ密教などが生まれます。
大乗仏教が中国に伝わるわけですが、そこで中国の思想とくに老荘思想と融合して新たな仏教、中国仏教が生まれます。
それが禅宗と浄土宗です。
禅宗は中国で大きく花が開きそれが日本にも伝わり、日本文化にも多大な影響を与えます。
浄土宗は中国よりも日本で大きく発展しました。
自然法爾は老荘思想とかなり近しい概念といえると思います。
老荘思想を説明するのは難しいのですが、一言でいうと、「無為自然」。
無為自然とは人間のさかしらな知恵を捨てて、大いなる自然の法則に沿った生き方をしようというものです。
ことさらに人間のさかしらな知恵を否定する禅宗、阿弥陀仏にすべてをゆだねる浄土宗、一見すると全く反対の宗派に思えますが、両方とも老荘思想の影響を受けているというのは面白いですね。
周易と老子(2023年8月)
私は鍼灸を業としているものですが、ライフワークとして東洋思想を学んでいます。
東洋思想は東洋医学のバックボーンでもありますので、東洋医学を学ぶ者はいづれ学ぶ必要があるのですが、鍼灸を抜きにしても面白いものです。
周易にしても老子にしても色々解釈の余地があり、個人的には私的に色々解釈をして楽しんでいます。
周易は面白いもので、儒教の重要な経典であり、儒教とは相反する老荘思想においても大事な経典となっています。
周易はもともとは占いですがそれを哲学まで高めたのが儒教になります。
あくまで私的な解釈ですが、生き方として周易を考えるならば、二つの道を示しているように思います。
一つは能動的に理性的に教え導き命令する父なる乾の道、もう一つは受動的に共感的に育て癒す母なる坤の道。
なので地天泰という上のものがへりくだって下のものと交流するある意味慈愛に満ちた卦があるかとおもえば、火雷噬ゴウのように邪魔なものは断固として排除する(獄を用いるに利し)非常に強権的な卦もあります。
この背反する二つの道を時と場合によって使い分け、全体としての調和を実現するのが周易の基本的な考え方だと思います。
老子は一言でいうと無為自然、人間のさかしらな考えを捨てて自然に沿った生き方をしようというものです。
あくまで私的な解釈ですが、先ほどの周易との関連でいえば、母なる坤の道こそが唯一の無為自然の道と老子は述べているように思います。
老子では儒教的なものを否定しますが、それは学ぶこと、規範を作ること、命令すること、いづれも父なる乾の道です。
老子が理想とするのは女性、水、赤子、小国寡民など柔弱なるもので、一見すると弱いものばかりですが、それがしなやかな強さを持ち、剛強なものに勝つといいます。
周易の母なる坤の道と老子の無為自然の道は全く同じとは言えないかもしれませんが、かなり近いものだと思います。
老子と周易、一見すると関連性が無いように思えても視点を変えてみればつながりが見えてくる、面白いですね。
温故知新(2023年7月)
温故知新とは「昔のことを研究して新しい知識や道理を知ること」ですが、伝統の知恵には宝物がたくさんあると思います。
もちろん鰯の頭も信心からではないですが、無批判に何でも信じると危険なこともあります。
宝物とゴミをきちんと区別する目を持たなくてはならないと思います。
TCH(Tooth Contacting Habit(歯列接触癖))という上下の歯を"持続的に" 接触させる癖があります。
上下の歯が接触する程度の力でも口を閉じる筋肉は働いてしまうため顎関節への負担が増え様々な不調を引き起こす原因になります。
解消法としては「歯を離す」と書いた付箋をテレビなどに貼り、歯を離す習慣付けを行うというものです。
その他に舌先を上の歯と上顎の間につけるというのがあります。
実はこれ舌砥上顎といって気功にもあります。
気功では督脈と任脈をつなげて気の流れをよくすると説明されます。
舌砥上顎のほかにも、立身中正、虚領頂頸など重要なものが気功にあります。
鎌田 實先生の著作などで書かれているかかと落とし体操も八段錦という気功体操のなかにあります。
背後七顛百病消というのものですが、腎を高めて万病を治すとされていますが、腎は東洋医学的には骨と関係がありますので骨粗しょう症予防に東洋医学的にも効果的だと思います。
伝統の知識を改めて見直すことも大事だと思います。
鍼の響き(2023年6月)
「鍼の響き」とは鍼治療によって、重だるい感じ、締め付ける感じ、温かい感じ、冷える感じなど患者さんが感じるものです。
中国では「得気」といいます。
得気(鍼の響き)が無いと効果がないという流派もありますが、必ずしも必要というわけではなく、得気(鍼の響き)が無くても十分効果はあります。
また鍼の響き(得気)が好きという患者さんもいますが、鍼の響き(得気)が苦手な患者様も多くおられます。
鍼の響き(得気)とは関係なく、古典には「気至」という言葉が有ります。
「その気至ること、釣針へ魚のかかるが如く、意をもってこれをうかがうべし」
柳谷素霊はその鍼灸師の手指を通して触知する感覚を鍼妙と表現しました。
藤本先生はオ血はスカスカした軽石、湿痰は粘っこい、気滞はすぐ締め付ける感じと邪実によって嗅ぎ分けていました。
私は邪気をチカッとした熱感として感じることが多いです。
いづれにしても、鍼の響き(得気)はそれほど気にする必要は無いと思いますが、気至(鍼妙)は非常に大事であると思います。
易の話のつづき(2023年5月)
前回の易の説明で足りないところがあったみたいなので、今回は前回の補足をさせていただきます。
艮(山)の卦のコアイメージは「覆いかぶさるようにして動かないように押し止める」と前回説明しましたが、艮の卦の「止まる」は分かるが「覆いかぶさる」はどういうことか、とのことですが、例えば山水蒙という卦がありますが、外卦が艮(山)、内卦が坎(水)となります。
コアイメージでは坎(水)は「解決しなければならない問題、困難」となります。
山水蒙をコアイメージで解くと、内に問題があるが、外の艮が覆いかぶさっている。つまり内なる問題が外からフタをされて見えなくなっている、と解釈できます。
蒙は童蒙という言葉もありますが、世間知らず、若気の至りというのに近い、自分の欠点が分からず失敗を犯す可能性がある、ということです。
なので蒙を啓く、啓蒙が大切となります。
あと、梅花心易についてですが、前回述べませんでした。
前回は卦名や卦辞(おみくじを引いたときに書いてある説明文のようなもの)を中心に判断する周易、四柱推命のように得られた卦から自動的に干支を配して五行的(相生や相克)に占う断易(五行易)を述べました。
周易は卦名や卦辞・爻辞で判断するのですが、判断しづらいケースが多い、その為漢の時代に象数という概念で易学上の発展がありました。
象とは現実世界のもの、数とは概念化された本質、ここでは八卦のこと、つまり現実世界のもの一つ一つを全て八卦に分類していくというものです。
それによってそれまでよりも占いの判断がしやすくなりましたが、それでも吉凶の判断が難しい場合もあります。
そのような中で断易(五行易)は明確に吉凶が判断できる利点がありますが、手順に従って干支を配したり六親を配したりと手順が煩雑な面や卦象や卦辞など周易を全く無視している面もあります。
そして梅花心易ですが、梅花心易は立卦(得卦)の方法がこれまでと全く異なります。
周易も断易(五行易)も筮竹やコイン(又はサイコロ)によって、卦を得ます。
梅花心易は現実の現象から卦を立てます。
例えば若い男(艮三)が南(離火)から来た場合に、山火賁という卦を得るというものです。
これは易学上からは大きな転換で、数(ある意味神意)から象(現実世界)を理解するという流れから、象(現実世界)から数(ある意味神意)を理解する流れができたということです。
占卦(得た卦の解釈)としては得た卦を体と用に分け、変卦や互卦も参考に五行的(相生や相克)に体が強まれば吉、体が弱まれば凶とします。
また、卦辞や爻辞も参考にします。
よって占卦(得た卦の解釈)としては周易と断易(五行易)の合わさったものといえます。
ただ、梅花心易は略筮法と同じ一爻変となりますが、本筮法や中筮法では変爻が六爻全てになったり、変爻が無い場合もあります。
易学上としてはこちらの方が本来の易の姿ではないかという問題もあります。
以上、前回の補足をさせていただきました。
山沢損と風雷益(2023年4月)
今回は易についてです。
易は元々占いとして始まりました。
その後、陰陽という宇宙の法則を表しているとされ、人がどう生きるにかという哲学・思想としても発展します。
東洋医学では易の法則から医学の法則を見つけ出そうという医易学という学問もあります。
易の構成としては、太極から陰陽が生まれ、その陰陽がそれぞれ陰陽に分かれて四象が生まれ、四象がそれぞれ陰陽に分かれて八卦が生じます。
その八卦どうしの組み合わせ、64卦で宇宙全ての陰陽法則が表せるとしています。
占いとしては、卦を出して、卦名や卦辞(おみくじを引いたときに書いてある説明文のようなもの)が64卦それぞれに書かれているのを参考にして占います。
実際に占ってみますと卦辞などが難しく占いを判断しづらいという面があります。
生年月日時間から自動的に干支を配して占う四柱推命という占いがありますが、得られた卦から自動的に干支を配して占う断易(五行易ともいう)があります、これは占いの判断がしやすいという利点があります。
しかしながら四柱推命のように占うので本来の易の陰陽の法則をきちんと表しているのかという面があります。
ここでは試論として、易の64卦は8卦同士の組み合わせとして捉え、8卦それぞれにコアイメージを当てはめ、そのコアイメージから64卦(ここでは山沢損と風雷益)を読み解いてみたいと思います。
山沢損
易書などを読むと山沢損は地天泰の下の一陽を上に与えたもの、自分を減らして他人に与える、「損して得取れ」などと書かれています。
これをコアイメージで読み解いてみると、山(艮)の卦のコアイメージは「覆いかぶさるようにして動かないように押し止める」。
沢(兌)の卦は元々は砂漠のオアシス、湧き水の出る沢で人々が集まり生活を豊かにする、喜びですが、易では享楽という悪い意味合いでも使われます。コアイメージは「喜び、享楽、欲望」。
山沢損をコアイメージで読み解くと「内なる喜び・欲望を外に出ないように抑える」つまり禁欲というようなイメージになります。
ことわざの「損して得取れ」も間違いではありませんが、「若い時の苦労は買ってもせよ」のほうがコアイメージ的には近い感じがします。
一時的に我慢をしよう。そしてその間に自分の力を増強しようというものです。
それゆえ、卦名は損というどちらかというと悪い名なのに、易書などでは吉の卦として書かれています。
易はタイムスパンが長いので最終的に得をするにはどうすれば良いのかという視点で書かれています。
風雷益
易書などを読むと風雷益は天地否の上の一陽が下に入ったもの、上のものが民に施しをしたもの、などと書かれています。
これをコアイメージで読み解いてみると、風(巽)の卦のコアイメージは「一定の力で押し続ける、隙間があればそこに入り込んで押し続ける」。
雷(震)の卦のコアイメージは「今まで動いていなかったものが動き始める、ビーンビーンとした振動」。
風雷益の卦をコアイメージで読み解いてみると、「動き始めたものが背中を押されている」追い風に乗っているというようなイメージになります。
易書で大吉と書かれているのもうなずけます。
今回はコアイメージで山沢損と風雷益の卦を読み解いてみました。
あくまで試論ですが、易の理解の一助になればと思います。
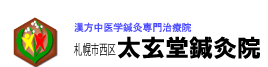
 鍼灸・漢方・東洋医学・東洋思想・気功編メニューへ戻る
鍼灸・漢方・東洋医学・東洋思想・気功編メニューへ戻る