「院長の独り言」ジャンル別
「院長の独り言」ジャンル別~鍼灸・漢方・東洋医学・東洋思想・気功編~
鍼灸・漢方・東洋医学・東洋思想・気功編 ―2005年-2007年―
- 伝統鍼灸について思ったこと(2007年12月)
- 徳川家康が天下を取った陰には・・・意外や意外家康は漢方の専門家!(2007年10月)
- 『ホジュン ~宮廷医官への道~』(2007年9月)
- 漢方薬では、「毒+毒=無毒?」なんてことも(2007年7月)(2007年7月)
- 東洋医学の基礎理論「陰陽理論」について(2007年6月)
- 日本の鍼と中国の鍼(2007年3月)
- 環境の変化と脈の関係(2007年2月)
- 医術の心 ~チャングムの誓いから~(2006年10月)
- 寒さと脈の関係(2006年10月)
- 東洋医学で六月病を考える(2006年6月)
- 紫河車 ~胎盤が漢方薬に~(2006年5月)
- 東洋医学の重要な診断法「脈診」について(2006年4月)
- 再び恬淡虚無(てんたんきょむ)(2006年4月)
- 恬淡虚無(てんたんきょむ)(2006年3月)
- 漢方資料館 草木庵(2006年2月)
- 暦と自然のリズム(2006年1月)
- 「宮廷女官 チャングムの誓い」をご存知ですか?(2006年1月)
- 「カゼ」について(2005年12月)
- 心持の大事 ~夢分流打鍼術から~(2005年9月)
伝統鍼灸について思ったこと(2007年12月)
10月27日(土)・28(日)に日本伝統鍼灸学会学術大会が札幌で行われました。
北海道で伝統鍼灸学会が行われるのは初めてのことで、私もスタッフとして微力ながらお手伝いをさせていただきました。
通常地方でこのような学会が行われると300人ぐらい集まるのが相場なのだそうですが今回の北海道大会では700人を越える人数が集まりました。
東京の大会でも800人を越えたことは無いそうですので東京に並ぶほどの人数が集まったことになります。
これを機に北海道でますます伝統医学・鍼灸医学が発展すればと思いますし、伝統医学・鍼灸医学に対する期待の大きさを感じざるえません。
昨今、日本の伝統医学・伝統鍼灸を見直そうという動きがあります。
中国は中医学を世界に発信していますし、韓国も独自の韓医学を打ち出しています。
そんななか日本は各流派がバラバラにあるだけで日本独自の伝統医学・伝統鍼灸というものを打ち出せないでいる。
だから早く日本独自の伝統医学・伝統鍼灸を打ち建てようというものです。
私も日本独自の伝統医学・伝統鍼灸とは何かを考えることは大賛成です。
しかし、あまり早急に結論を急がないほうがいいと思っています。
日本の伝統医学・伝統鍼灸を選定するにはそのための基準となる物差しが必要となります。
その物差しを何処に置くかそれによって全然異なったものになる恐れがあるからです。
実際中国においても現代中医学に対して中医学内部から異論反論が僅かながらですが出はじめているそうです。
現代中医学は毛沢東の時代それまで様々あった流派を唯物史観に基づいてまとめ上げたものです。
当然その切り捨てられたものの中にも大切なものがあったのではないかと思います。
勿論、玉虫色の理論など出来る訳もありませんが切り落としてはいけないもの、伝統鍼灸の本質についてはじっくりと考える必要があると思います。
徳川家康が天下を取った陰には・・・意外や意外家康は漢方の専門家!(2007年10月)
徳川家康を知らない人はいないと思いますが、豊臣秀吉の後に天下を取り、江戸幕府300年(実際は264年)の礎を築いた人です。
家康は60歳を過ぎてから天下を取りました。
そしてその後75歳で亡くなるまで江戸幕府の基礎を固めるため元気に活躍していました。
そんな家康は健康に人一倍気を遣っていました。食事も戦場にいた頃の食生活を基本的には崩しませんでした。
死因といわれる鯛の天麩羅(てんぷら)は滅多にない贅沢だったようです。
面白いことに家康は薬にも詳しく自分で薬を処方して飲んでいたようです。
一説によるとその知識は専門家が舌を巻くほどのもので孫の家光の大病を治したともいわれています。
家康がつくった烏犀円(うさいえん)という漢方薬が現在まで伝わっています。
(彰考館 徳川博物館 〒310-0912 茨城県水戸市見川1-1215-1 Tel : 029-241-2721)
烏犀円は『和剤局方』(わざいきょくほう:中国・宋の時代の書物)という書物に書かれており、『和剤局方』には烏犀円の他現在でも使われている漢方薬が沢山載っています。
家康はこの書物を参考にして東洋医学を勉強し健康管理をしていたようです。
家康が天下を取ったその陰には東洋医学のちからがあったのかも知れませんね。
『ホジュン ~宮廷医官への道~』(2007年9月)
『宮廷女官チャングムの誓い 』について以前ご紹介させていただきましたが、チャングムを演出をしたイ・ビョンフンさんがチャングムの前に製作したテレビドラマで『ホジュン ~宮廷医官への道~』というのがあります。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ホ・ジュンは実在の人で低い身分として生まれますが優れた医術で当時の医者としては最高の位まで登り詰め、その後『東医宝鑑』という素晴らしい本を著述します。
ドラマではチャングムと同じように漢方薬や鍼の場面が沢山出て来ますし、ストーリー展開も面白くチャングムと同じようにグイグイストーリーに引き込まれます。(ストーリーを面白くするために幾分フィクションが入っていますが・・・。)
チャングムを見た方はチャングムに出ていた役者さんがホ・ジュンにも結構出ているのでそれも楽しめます。
チャングムとホ・ジュンは時代としてはチャングムのほうが少し先ですが一部重なっています。
チャングムは李氏朝鮮王朝の10代燕山君から11代中宗の時代の話で中宗に仕えました。
ホ・ジュンが仕えたのは14代宣祖と15代光海君ですが生まれたのは中宗の時代です。 私は韓国の歴史をよく知りませんが歴史を知っていればもっと楽しめるかもしれませんね。
興味のある方はDVDが出ていますので見られては如何でしょうか。
漢方薬では、「毒+毒=無毒?」なんてことも(2007年7月)
漢方と西洋の薬物学の考えかたの違いの一つに漢方ではそれぞれの生薬の関係性を調べそれが複合的にどのように働くかを重要視します。
西洋医学ではあくまで一つの薬物がどのように働くかを考えます。
例えば炎症を抑える薬と胃の薬を出したとすると、その二つの薬が合わさって複合的にどのように働くかということは基本的に西洋医学では考えません。いわば1+1=2の医学なのです。
一方漢方医学では生薬の組み合わせにより1+1=3や4になったり、逆に1+1=0やマイナスになったりします。
面白い例として「萬菫不殺(まんきんふさつ)」というのがあります。
萬(サソリ)と菫(トリカブト)を合わせると面白いことに毒性が減るのです。
全ての毒物が合わせると毒性が減るということではなくて、サソリとトリカブトの組み合わせは互いの生薬の働きを弱めるため毒性が弱まるのです。
生薬によってはお互いの働きを強める組み合わせもあり、場合によっては1+1=3や4になる場合もあるのです。
面白いですね。
東洋医学の基礎理論「陰陽理論」について(2007年6月)
陰陽理論は東洋思想・東洋医学において根本的な理論です。
陰陽理論においては陰陽は対立しながら統一されているとか陰陽が相互に転化するとされています。
現代の我々にとって陰陽理論は一見すると矛盾した非論理的なもののように思えますがこれは陰陽理論が通常日常的に私達が使用している理論とはその論理構造に大きな違いがあるためだと思われます。
古典に「陰をもって陽に引き、陽をもって陰に引き、右をもって左を治し、左を持って右を治す、・・・」というのがあります。
右の病は右で治し、上の病は上で治すのが通常でありましょうが、右の病を左で治し、上の病を下で治すということを述べています。
このことを考えると話が飛びますがユークリッド幾何学と非ユークリッド幾何学の違いに私は思いを馳せてしまいます。
ユークリッド幾何学とは平面における図形の世界です。非ユークリッド幾何学とはユークリッド幾何学以外の世界です。
私達に馴染みのあるユークリッド幾何学の世界では平行な2直線は交わることがありません。
しかし非ユークリッド幾何学の世界では、例えば球面の世界では平行な2直線は交わることもあるのです。
地球儀の経線と緯線を考えてもらうといずれも平行な直線でありますが経線は北極点などで必ず交わり緯線は交わりません。
状況(条件)によって平行な2直線は交わったり交わらなかったりするのです。
非ユークリッド幾何学はあまり使われませんが、ユークリッド幾何学のような平面世界ではなく非ユークリッド幾何学の世界のほうが現実の世界により近いと思います。
リアルな現実の世界は矛盾に満ちた世界であります。
陰陽理論はその矛盾に満ちた世界を矛盾無く説明出来る非常に優れた理論だと思います。
日本の鍼と中国の鍼(2007年3月)
一月に友人に誘われてある中国人の鍼灸の先生の講演を聴きいいきました。
実技も見ることが出来てとても面白かったのですが、中国の鍼と日本の鍼の違いというものを改めて認識させられました。
それは中国人の先生は鍼を刺すときツボを指で探して確認をしないということでした。
同じ鍼でも中国と日本では違うんです。それは鍼の形だけでなく技術的な面や理論的な面まで違いがあります。
一般的には中国の鍼は理論に優れ、日本の鍼は技術に優れているといいます。
これはおそらく日本の鍼は身体の状態を指目とも言いますが指頭により探り、その身体の反応を変に理屈を付けるのではなく感じ取りそれをそのまま元の状態にに返してあげる、それが良いとか悪いとかは別にしておそらくそういう感性を大事にする鍼なのでしょう。
環境の変化と脈の関係(2007年2月)
今年は例年にないほど暖冬ですね。
2月6日から始まった「第58回さっぽろ雪まつり」も暖冬の影響を受けて溶けかかっている雪像もありました。
地球はやっぱりどこかおかしくなってきているのでしょうか。
いま地球の温暖化が大きな問題となっていますが、今のままのペースで進むと今世紀末には北極の氷が夏はすべて溶けてしまうそうです。
環境問題は私達人間にとって大きな問題ですね。
東洋医学では天候や季節などの環境が人間に大きな影響を与えるとしています。 例えば春には弦脈、夏には洪脈など季節によって脈が異なり、季節は人体に大きな影響を与えます。
また風・寒・暑・湿・燥・火などの天候が過不足することによっても病を引き起こす要因になったりします。
この様な天候についての東洋医学における理論が運気論といわれるものです。
黄帝内経という東洋医学のバイブルにも運気論について書かれています。
天元紀大論、五運行大論、六微旨大論、気交変大論、至真要大論、六元正紀大論、五常政大論などがそれです。
運気論は自然界の気候の変化と人体との関係を探る理論です。
人の健康に寄与する仕事をしている私達鍼灸師にとっても環境問題は無関心ではいられない問題です。
医術の心 ~チャングムの誓いから~(2006年10月)
『チャングムの誓い』も全54話のうちもう51話まで終わってしまいあと僅かになりました。今回の51話のタイトルは「医術の心」でした。
天然痘にあきらめることなく立ち向かうチャングム、そしてとうとう天然痘を治します。そんなチャングムを見て師でもあり医局長のシン・イクピルは王の主治医にチャングムがなることに同意し王に上奏します。その上奏で、シン・イクピルはチャングムは母の心で治療にあたって素晴らしいと言います。
本当に素晴らしいことですよね。
そういえば、東洋医学のバイブル、黄帝内経の霊枢・九鍼十二原篇にも黄帝の言葉に「余子萬民」というのがあります。
そのまま読めば「余(よ)は萬民(ばんみん)を子(こ)とす。」ですが、「余は萬民を愛(いつく)しむ。」と読みます。
「子」を「愛(いつく)しむ」と読ませているところが面白いですよね。
「子」は名詞ですが、古代漢語では名詞を動詞としても使うんですよね。
現代中国語では名詞を動詞として使わないのでそこが古代漢語と現代中国語の大きな違いの一つです。
患者をわが子と思って治療する、それが医術の心ということでしょうね。
『チャングムの誓い』DVD
(※第46話「医局長の遺書」から第54話「我が道」までを収録。)
寒さと脈の関係(2006年10月)
10月も後半に入り北海道は大分寒くなってきました。札幌でも平野はまだですが手稲山などでは初冠雪がありました。
私は日々の治療で患者さんの脈を診ていますが、このところ脈が浮いている人が多くなりました。
『傷寒論』という2000年ほど前の東洋医学の本にはカゼを引くと脈が浮くと記載されており、その通りで脈の浮いている人の多くは何らかの風邪(かぜ)の症状があります。
また明らかな風邪(かぜ)症状が出ていない人でも、よく診てみると風邪(かぜ)に反応するツボに反応が出ているので軽く風邪(かぜ)を引いている状態なんです。
大いなる自然と人の身体は密接に繋がっていて、それを知っている東洋医学はやっぱり素晴らしいですね。
東洋医学で六月病を考える(2006年6月)
六月ももう半ばになりましたが、皆さんは六月病って知っていますか?
五月病は皆さん知ってらっしゃると思いますが、大学に入りたての学生などに五月ごろに見られる症状です。
六月病も同じものなのですが、新社会人などは新人研修が終わって実際の仕事をはじめた後の六月ごろに症状が出ることが多いため六月病とも呼ばれています。
五月病、六月病どちらも西洋医学では適応障害といい、実際は五月六月に限らずどの時期でも環境が大きく変わるなどのストレスによってなります。
症状としては、なんとなく気が滅入って無気力、何をするにも面倒で億劫、興味や関心がわかない、思考力や判断力がもてない、不安や焦りを感じる、イライラする、強い疲労感、朝起きられない、食欲不振、嘔気、便秘、下痢、腹痛、不眠、頭痛、めまい、動悸などです。
六月病は東洋医学でもストレスが原因と考え、簡単にいうと肝の臓と脾の臓の機能障害と考えます。
(ちなみに、東洋医学の肝の臓、脾の臓と西洋医学の肝臓、脾臓とは同じものではありません。)
鍼灸や漢方などの東洋医学での治療によって五月病、六月病などの適応障害も改善されますのでお悩みの方は一度試されてはいかがでしょうか。
紫河車 ~胎盤が漢方薬に~(2006年5月)
皆さん、「紫河車」って知ってます?
紫河車は漢方薬で使う生薬なのですが、実は胎盤のことなんです。
ちょとグロテスクに思われるかもしれませんが、胎盤は現代医学でもプラセンタ(胎盤エキス)として使われ細胞賦活・免疫賦活・抗炎症・抗アレルギーなど様々な効果が確認されています。
紫河車という名前ですがこれは仙道(気功の大もと)の修行法の一つの名です。つまり、その修行をしたのと同じくらい効果があるということでその名がついたのでしょう。
個人的に面白いと思ったのは、中国の薬草の本である本草綱目(ほんぞうこうもく)によると別名が、胎衣・混沌衣・佛袈裟・仙人衣などと書かれていることです。
胎衣は胎つまり胎児を包む衣(胎盤)という意味です。
そうすると混沌衣は混沌の衣つまり赤ちゃんが混沌ということですね。 赤ちゃんが混沌ということはもっといえば、人間の存在そのものが混沌ということでしょう。
矛盾を含んだ人間の存在そのものが混沌である。
意味深いですよね~。
また佛袈裟は佛(仏)の袈裟(衣)であるという意味ですし、仙人衣も同じように仙人の衣という意味です。
すべてのものに仏性あり。
人は生まれながらにして仏であり仙人であるということでしょう。
こんなところにも、中国思想の一端が窺えて面白いですね。
東洋医学の重要な診断法「脈診」について(2006年4月)
東洋医学の重要な診断法の1つに脈診があります。
中国や日本の伝奇小説や古典などを読むと東洋医学の医者が(昔は西洋医学はないので皆東洋医学なのですが)患者の脈を診るだけで患者のすべてが解かるという話がでてきます。
もっとすごいのになると、脈を診て天変地異を予言したりという話まででてきます。
多くは小説の類の話ですが実際にあった昔の名人の伝説的な話も秘伝書を通していくつかは現在まで残っています。
このように古来から東洋の文化のなかで脈というものの位置づけが他の診断法(問診、舌診、腹診など)とは明らかに異なっていました。
その要因として特に中国において患者の肌に直接触れるということが特に貴人(身分の高い人)に対して行いにくかったという文化的側面から脈診という診断法が重んじられたということもあるでしょう。
しかし私はもっと大きな要因として東洋の気の思想があると思います。
気の思想とは簡単にいうと、世界は目に見えるものと目に見えないものから成り立ち、目にはっきりとは見えない何か(気)が世界を動かしている中心であるというものです。
昔の人にとって脈というものは、はっきりとは目に見えないけれども感じることのできる何かだったのでしょう。
ですから、脈というものが生命の本質である気を直接的に表していると考え、脈診という診断法が他の診断法とは異なる位置づけを与えられていたのだと思います。
再び恬淡虚無(てんたんきょむ)(2006年4月)
恬淡虚無(てんたんきょむ)の一つ一つの漢字を調べてみました。
恬は、やすらか。平然として落ち着いている。平気でいる。しずか。うすい。起伏が無く落ち着いている。しずかな心。などの意味があります。 恬は心(意味)+舌(音・意味)から成り立ち、舌の平らな面のようにペッタリと落ち着いた心ということからできた会意兼形声文字です。
ちなみに会意文字とはその漢字が二つ以上の意味を表す漢字からできているということです。
形声文字とはその漢字が意味を表す部分と音を表す部分の二つからできているということです。
会意兼形声文字とはその二つが合わさった文字ということです。
淡は、あわい。うすい。刺激が無いさま。色や味がうすいさま。あっさりしたさま。あっさりとしたもの。欲望がうすいさま。などの意味があります。
淡は水(意味)+炎(音)から成り立ち、静かに安定していて刺激がないことからできた形声文字です。
水と炎の組み合わせというのも面白いですね。炎は音のみで意味は関係ないのですが、燃え盛る炎を水で消しているのかなと想像してみるのも面白いです。
虚は、むなしい。くぼんで中があいているさま。転じて中身がなくうつろであるさま。から。むなしくする。うつろにする。からにする。いつわり。中身がうつろな。実質がともなわないさま。などの意味があります。
虚は丘の原字(両側に丘があり中央にくぼんだ空地があるさま)+コ(音)から成り立ち、くぼんでなかがうつろなさまからできた形声文字です。
無は、ない。形や姿がない。物や事がらが存在しない。なかれ。ないこと。老子や荘子の考えで、現実の現象以前のもので有を生み出すもとになるもの。などの意味があります。
無の甲骨文字は人が両手に飾りを持って舞うさまで、後の舞の原字でもある。無は亡(ない:意味)+舞の略体(音・意味)からなる会意兼形声文字で蕪(茂って見えない)や舞(ない物を神に求めようとして神楽をまう)などと同系のことばで見えなくないものです。
ここで、虚や無と同じように東洋思想でよく使われる空についても調べてみました。
空は、むなしい。穴があいている。中に何もなくつきぬけている。からっぽ。うつろ。そら。おおぞら。地上のなにもないくうかん。仏教で意識(色相)をこえてすべてをゼロとみなす悟りの境地。いっさいのものは因縁によって生じるもので不変の実体はないという仏教の根本原理の1つ。などの意味があります。
空は穴(意味)+工(音・意味:つきぬく)から成り立ち、つきぬけて穴があき中に何もないことを示す会意兼形声文字です。
空とか無とか虚とかは一見すると同じような意味ですが、元々のイメージでは、空、虚、無それぞれ微妙なニュアンスの違いがあります。
このような漢字の微妙な違いを知ることは東洋医学・東洋思想を知るうえで必要なことだと思いますし、また楽しいことでもありますね。
参考文献
『漢和大字典』(藤堂明保、学習研究社)
関連記事
「恬淡虚無(てんたんきょむ)」(2006年3月)
恬淡虚無(てんたんきょむ)(2006年3月)
現代はストレス社会といわれて久しいですが、現代社会に生きる私達は何らかの形でストレスを受けています。
いうまでもないことですが、ストレスが身体に及ぼす影響には大きなものがあります。
東洋医学のバイブルである『黄帝内経』(こうていだいけい)のなかにもこのことは書かれています。
「恬淡虚無(てんたんきょむ)なれば、真気これに従い、精神内に守らば、病いずくんぞ従い来たらん。」ということばがそれです。
簡単にいうと、恬淡虚無(てんたんきょむ)は「あっさりして物事にこだわらないこと」であり、そうすれば真気(自然治癒力)は良く働きます。このように精神が安定していれば病気になることはありません、ということです。
二千年も前から東洋医学はストレスと身体、心と身体について知っていたんですね。
関連記事
「再び恬淡虚無(てんたんきょむ)」(2006年4月)
漢方資料館 草木庵(2006年2月)
昨年のことですが、友人に連れられて「漢方資料館 草木庵」に行きました。
場所は札幌の平岸で、生薬の標本が六百五十種二千五百数点が展示されています。 今では貴重な熊胆(くまのい)や自然の人参や一角などがあり、その他医心方、本草図譜、千金方などの書籍も展示されていました。
北海道にこのような資料館があるとは知りませんでしたし、こういう資料館があるということは大変素晴らしいことです。 しかも、この資料館は無料で入館ができます。
漢方薬でどんなものが使われているか、実際に原材料である生薬の実物を見るとまた違った感じがしますね。
東洋医学に興味がある人は一度行かれてみてはいかがでしょうか?
漢方資料館 草木庵
住所:北海道札幌市豊平区平岸2-5-2-4
電話:011-831-6222
開館時間:10:00~16:00 (土日祝休み)
※事前に電話での予約が必要です。
暦と自然のリズム(2006年1月)
昨日、2006年1月29日が旧正月でした。 旧暦では昨日から新しい年というわけですね。
暦というのも難しいですね。
新暦と旧暦では当然年の変わり目は違いますが、占いなどでは立春(2月4日頃)を年の境としますし、天の自然の運行と人体の関係を考えた運気論というものがあるのですがそれでは大寒(1月20日頃)を年の境とします。
暦は何故生まれたのでしょうか?
農耕を行う為ということでもあるのですが、私が思うに基本的に天人相関という考えがあって、人や植物、動物が天の自然の運行と関係している。だから人が自然のリズムに合わせて生きれるように暦を作ったのだと思います。
東洋医学のバイブル、黄帝内経ではそれぞれの季節による生活の仕方が書かれています。
ですから、自然のリズムに合った生活をしなければいけないということですね。
自然のリズムでよく耳にするのは月のリズムに犯罪や出産が関係しているということです。
満月の日に犯罪が多いといわれています。面白いことに気の狂ったという意味のルナテックという単語のルナは月という意味です。また新月や満月のときに出産が多いともいわれています。
暦を考えるうえで複雑なのは月のリズムだけではなく太陽のリズムなどもありそれぞれが異なるリズムで運行しているということです。
ですから、天の自然の運行のリズムを記述しようとしたら複雑にならざるえないのですね。
「宮廷女官 チャングムの誓い」をご存知ですか?(2006年1月)
みなさんは「宮廷女官 チャングムの誓い」をご覧になったことがあるでしょうか?
大変面白いので観たことのない人は是非観てほしいです。 NHK総合で毎週金曜日午後11時放送しています。全54話で次回1月20日(金曜日)が第14話になります。(昨年は土曜日の午後11時放送でした。)
物語は今から500年前の朝鮮王朝でヒロインのチャングムが母の遺志を継ぎ宮廷の女官となり、宮廷料理人の頂点を目指します。その後紆余曲折があり医女となったチャングムは多くの男性医師たちを退けて王の主治医となるというサクセスストーリーです。
チャングム(=長今)は実在の人物で朝鮮王朝第11代王中宗に仕えた女医として『朝鮮王朝実録』に載っているそうです。しかし、生没年や生い立ち、性格などについての記載は無く詳しいことは解かっていませんが、「余の体のことは女医(=チャングム)が知っている」という中宗の発言が記載されており、また「大長今(=偉大なる長今)」という名称が中宗から長今(チャングム)に与えられたことから当時非常に優れた人物で重用されていたようです。
ドラマ前半でチャングムが宮廷料理人として描かれていますがこれは保養食が上手に作れるならきっと料理も上手だっただろうという監督の憶測からのようです。でもこのお蔭でよりドラマチックな展開になっています。
チャングムのもう一つの見所は番組で出てくる宮廷料理や東洋医学などの文化的側面が忠実に再現されているということです。例えば鍼で使われるツボなどもそのような症状で実際に使われるようなツボが使われています。また庶民の生活や階級・身分制度など当時の文化を知ることが出来るという意味でも面白いです。
私は決してNHKの回し者ではありませんが(笑)、皆さん、是非「宮廷女官 チャングムの誓い」を観ましょう。
「カゼ」について(2005年12月)
もう12月ですね、3月まで奈良にいた私にとっては久しぶりの北海道の冬なので今から戦々恐々としています。北海道の冬は、雪はねは大変ですし、家の中は暖かいですが外はとても寒いですので、今から春が待ちどうしいです。
さて、冬になるとどうしても「カゼ」を引きやすくなりますね。東洋医学では「カゼ」について大きくは傷寒(しょうかん:風寒の邪によるもの)と温病(うんびょう:風熱の邪によるもの)があります。
私たちが通常さむけを伴なっておこる「カゼ」は傷寒です。1800年ほど前に書かれた『傷寒論』(しょうかんろん)という本に「カゼ」の治療法が詳しく載っています。落語に出てくる「葛根湯」もこの本に出てきます。傷寒の「カゼ」も初期の状態を大きく分けると麻黄湯(まおうとう)と桂枝湯(けいしとう)のタイプに分かれます。体質などにより漢方薬が異なるのです。
皆さんは「カゼ」を引くと病院に行かれて西洋薬で治される方が多いと思いますが、鍼灸や漢方も有用な治療法の一つです。病院でなかなか治らないときなど試してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、家庭で出来る簡単なものとしては「カゼ」の引き始めでさむけがする場合に、長ネギの白根1本とショウガ15グラムをみじん切りし、味噌大さじ1とカップに一緒にいれ、熱湯を注ぎよくかき混ぜて飲むとか、梅干の黒焼きに醤油少々と熱い番茶を入れ飲むというのもあります。
「カゼ」の関連ページ
心持の大事 ~夢分流打鍼術から~(2005年9月)
9月11日に札幌コンベンションセンターで(社)北海道鍼灸師会主催の学術講演会が開かれました。私も午後1時からの藤本蓮風先生の夢分流打鍼術という、日本鍼灸の古流派についての特別講演に参加させていただきました。
私は藤本先生のもとで内弟子として学んでいましたので、夢分流についてはある程度の知識はありましたが、今回の講演を聞いて、夢分流のなかの「心もちの大事」ということの大切さを、改めて認識しなおしました。
夢分流を作った夢分翁は、もともと禅宗の僧侶でありましたが、自分の母の病気がなかなか治らなかったため鍼を学び、やがて独自の治療法を編み出しました。
夢分翁が自分の母を治したように、「病気が治ってほしいという一念」その純真な気持ちを忘れず、初心に帰り日々の治療にあたりたいと改めて思いました。
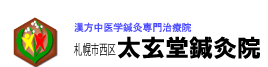
 鍼灸・漢方・東洋医学・東洋思想・気功編メニューへ戻る
鍼灸・漢方・東洋医学・東洋思想・気功編メニューへ戻る